2026.01.30
副業時代に経営者が知っておくべき税務知識と「副業300万円問題」の最新動向
2017(平成29)年の「働き方改革実行計画」で副業・兼業の促進が明確に示されて以来、柔軟な働き方がしやすい環境整備の一環として、副業を認める会社は増加しています。そのため、経営者にとっても、副業…
記帳は税務申告をするために不可欠な作業ですが、それだけにとどまりません。経理で把握できる数値は、経営環境を改善するための重要な指標となります。ただし、記帳作業を「税務申告のための作業」と捉えていると、申告期日に間に合えば良いと考えがちですが、「経営に活かす」ためには経営数値を早期に把握することが大切です。
経営数値とは、企業の財務状況を示す指標であり、売上高・利益率・資産負債のバランスなどが含まれます。これらは、経理が記帳・集計した数値で、決算書や試算表を通じて確認可能です。企業の運営状況を反映するだけでなく、戦略的な意思決定の根拠としても活用され、会社の経営成績や財政状態を表す重要なデータとなります。
試算表と決算書は、会社の財務状況を理解するための出発点であり、ビジネスの各種指標を正確に把握するための基礎となります。
試算表とは企業の収支状況を示す書類です。貸借対照表(B/S)は企業の資産や負債を一目で把握でき、損益計算書(P/L)は一定期間の収益・費用・利益を示します。これらを用いることで、企業の経営状況を総合的に把握し、戦略的な意思決定が可能となります。
決算書は、1年間の経営活動をまとめた資料であり、売上・利益・支出などの詳細な情報把握に不可欠です。企業の財務状況を総合的に示し、税務申告だけでなく、経営戦略の立案や金融機関との交渉に活用されます。
試算表の数字を早期に把握することで、会社の現状を素早く把握し、的確な経営判断につなげることができます。
例えば、プロジェクトの年間予算が決まっている場合は、使用可能残額を確認し、資金計画に基づく適切な調整が可能です。また、年間利益目標を設定している場合は、達成までの進捗を数値で把握し、今後の売上やコスト管理を功利的に進めることが可能になります。
予算数値と比較することで、達成状況が把握でき、経営判断や予算の見直しに役立てることができます。また、前期比較から業績の変化を分析すれば、改善点も明らかになります。重要なポイントは、早期に記帳し、最新の経営数値をもとに迅速な意思決定をおこなうことです。
経営数値から導き出される指標により、企業の財務状況や経営の健全性を分析できます。特に、中小企業の経営判断に役立つ指標として、収益性分析、安全性分析、生産性分析が挙げられます。
収益性分析は、企業の収益を生み出す力を評価する指標です。利益率や売上高を測定し、事業の採算性を分析します。中小企業で確認すべき代表的な指標である「売上高総利益率、売上高経常利益率、総資本利益率」の求め方について解説します。
売上高総利益率(粗利率)は、売上総利益が売上に占める割合を示す指標で、計算式は以下の通りです。
売上高総利益率(%)=(売上総利益÷売上高)×100
比率が高いほど利益が多いことを示します。しかし、業種によって大きく異なるため、単純な比較は困難です。例えば、サービス業は原価少なく人件費が主なコストとなるため粗利率は高くなりやすい一方、卸売業や小売業では仕入れた商品を販売するため粗利率が低くなる傾向にあります。
売上高経常利益率は、売上に占める経常利益の割合を表す指標で、以下の計算で求めます。
売上高経常利益率(%)=(経常利益÷売上高)×100
経常利益は、営業活動による利益に加えて、借入金の利息などの営業外損益も含みます。中小企業では、借入金の利息負担が大きいケースもあるため、経常利益は実質的な収益力を測る指標とも考えられます。業種や経営状況によって適正水準は異なりますが、一般的に10%あると安心とされています。
総資本利益率は、企業の資産をどれだけ効率的に運用し、利益を生み出しているかを見る指標です。
総資本利益率(%)=(当期純利益÷総資本)×100
総資本は、貸借対照表における「資産の部」の合計で、一般的に5%以上あると健全な運営とされています。ただし、業種により適正値は異なるため、同業他社との比較や過去の推移を確認しながら、目標設定することが重要です。
中小企業は規模が小さいため、利益率を高める工夫が求められます。また、指標に急激な変化がある場合には、原因の分析や改善対策の検討が不可欠です。
安全性分析では、会社の財政状態の安定を判断します。中小企業で、特に確認したい主な指標は、自己資本比率と流動比率です。
自己資本比率は、総資本に占める自己資本の割合を示す指標で、以下の計算式で求めます。
自己資本比率(%)=(自己資本÷総資本)×100
自己資本は、貸借対照表の「純資産の部」に該当し、資本金や繰越利益剰余金(過去の利益の累計)などを含みます。返済の必要がない資本であり、この比率が高いほど経営の安定性が高いとみなされます。中小企業では、最低30%以上、できれば60%あると優良とされるでしょう。しかしながら、自己資本比率の高さだけで「安心」だとは言い切れません。自己資本比率が高くても、現預金が少ないと資金不足を起こす可能性があるため、注意が必要です。
流動比率は、流動負債(買掛金など)に対する返済原資として、流動資産(現預金や売掛金など)がどのくらいの割合かを示す指標です。
流動比率(%)=(流動資産÷流動負債)×100
比率が高いと短期的な返済能力があるとみなされ、一般的に100%以上あれば安心とされます。ただし、流動資産には在庫などすぐには現金化できない項目も含まれます。資金繰りの安定性を判断する際は、流動資産が短期で資金化できるかどうかも注意しましょう。
生産性分析は、投下した資本が売上や利益をどれほど効率的に生み出しているかを評価する指標です。中小企業で確認すべき指標として、労働分配率が挙げられます。
労働分配率は、人件費が付加価値に占める割合を示し、以下の計算式で求められます。
労働分配率(%)=(人件費÷付加価値)×100
簡便的に、付加価値の代わりに粗利(売上総利益)で計算するケースもあります。この比率が低いほど、少ない人件費で多くの利益を生み出していることを示し、効率性が高いとされます。ただし、この数値は粗利率同様、業種によって異なる点に注意が必要です。
また、労働分配率を上げるために人件費を下げるとモチベーション低下を招きかねません。適正な労働分配率を維持しながら、企業の収益性と労働コストのバランスを管理することが大切です。
試算表にある数字から経営指標を計算するだけでなく、費用を「変動費」と「固定費」に分類し、損益分岐点売上高を把握することも重要です。
変動費とは売上に比例して増減する費用、固定費とは売上がなくても発生してしまう費用を指します。例えば、費用には(1)売上原価と(2)販売費及び一般管理費があり、これを変動費と固定費に分けることで、収益構造をより明確に分析できます。
固定費は売上がなくても発生するため、最低でもこの金額を超える利益を確保しないと営業利益がマイナスになります。売上のうち「利益がゼロになる」「固定費だけは回収できる」金額を損益分岐点売上高といい、適切な経営判断をおこなうための重要な経営指標となります。
経営数値の適切な計算には、正確な記帳データが欠かせません。今後の経営に生かすためには、決算・申告時期に間に合わせるのではなく、月次で記帳をおこないリアルタイムで必要な数値を把握することが重要です。これにより、経営判断の精度を高め、迅速な対応が可能となります。
しかし、中小企業ではリソースが限られていることから、記帳作業が後手にまわりがちです。そのような場合は、経理業務のアウトソーシングやクラウドツールの導入を検討することをおすすめします。
経理業務をアウトソーシングする際は、中小企業の経理を専門に扱う業者を探すことが肝要です。自社の規模や業種に合った業者に経理業務を依頼することで、以下のような利点が得られるでしょう。
専門知識と豊富なノウハウを生かした適切な仕訳記帳がおこなわれ、経理データの正確性が向上します。さらに、中小企業に多い「1人経理」では難しいダブルチェック機能の整備や属人化の解消も可能です。
売掛金・買掛金を適切に管理し、入金遅れや未回収金への早期対応が可能になります。さらに、キャッシュフローの管理を徹底することで、資金ショートを防ぎ、黒字倒産のリスクも大幅に軽減可能です。
クラウド型会計システムを導入すると、取引記録の取得から仕訳記帳、集計、さらには集計や分析も自動化します。経理データの精度向上と同時に、経理担当者の工数削減もでき、人の判断が必要となるコア業務にリソースを集中できます。
共有機能も利点の1つです。一元管理された経理データをスタッフ間で共有することで、情報の遅延や誤解を減らすことができるでしょう。また、経営者は現場の状況をリアルタイムで把握し、的確な意思決定を行うことが可能になります。
単なる効率化を超えた、経営状況の健全化を目指すDX導入は、以下の3ステップで進めましょう。
売上高総利益率や流動比率を基に、自社の課題を明確化します。過去の数値との比較をおこない、改善すべきポイントを特定することで、経営戦略の方向性を定めることが可能です。
リアルタイムで数値を確認できるクラウド型システムを導入し、目標値との差を検知することで、課題の早期発見が可能になります。さらに、社内で必要な情報をリアルタイムで共有でき、業務効率化と意思決定の迅速化に貢献します。
KPI(Key Performance Indicator・重要業績評価指標)は、目標達成度を定量的に測るための指標です。設定したKPIを継続的に評価しながら、運用フローの改善につなげましょう。PDCAサイクルを効率的に回すことで、経営戦略の精度を向上させ、持続的な成長を促進します。
経営数値を計算し、適切な経営判断をおこなうためには、早期の記帳が欠かせません。
月次で記帳し、最新の数値を確定させることで、会社の「現在の」状況を的確に把握できます。
ただし、リソース不足により記帳作業に手が回らない場合は、アウトソーシングやクラウドツールを活用すると良いでしょう。これにより、業務負担を軽減しながら正確な経営数値を継続的に把握できます。
さらに、税理士と顧問契約を結び、月次で数値を確認してもらうことで、専門的な分析や助言を受けることができます。より精度の高い経営判断をおこない、企業の成長を支える基盤を整えましょう。
弊社では、経理業務のアウトソーシングはもちろん、クラウドツールの選定や導入サポートもおこなっております。また、当サイトを運営する林会計事務所を通じて税理士の顧問契約についても、対応可能です。
まずは、貴社の状況を把握し、必要なツールやサポートを考えるところから始めてみてはいかがでしょうか。
神奈川 横浜・町田経理アウトソーシングオフィスは、経理・税務・経営に関するお客様のあらゆる課題を解決する総合会計事務所です。創業50年以上の歴史を持ち、約100名の専門家がお客様の事業を力強くサポートします。
約100名体制の経理・税務・経営のプロフェッショナルが、お客様の状況に合わせた最適なソリューションを提供します。複雑な課題も多角的な視点から解決に導き、お客様の成長を強力に後押しします。
会計・経理業務から給与計算、各種コンサルティングまで、DX化推進とアウトソーシングを支援します。これにより、お客様は本業に集中でき、業務の効率化と人件費などのコスト削減を同時に実現します。
最新のクラウド会計システムを積極的に活用し、経営数値のリアルタイムな把握を可能にします。これにより、迅速な経営判断をサポートし、事業の成長を加速させます。
経理・税務の基本サポートに加え、会社設立、相続、さらには医療機関や社会福祉法人に特化した専門的なコンサルティングも提供します。お客様の事業フェーズや業界に合わせたきめ細やかなサポートが可能です。
バックオフィスの改善や、経理・労務、経営に関するお悩みを信頼できる専門集団に任せたい経営者の方は、ぜひお問い合わせください。



経理体制の
ヒアリング(無料)

貴社の課題解決の
ためのご提案

ご契約
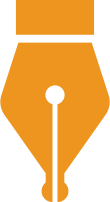
貴社の業務フローの
改善サポートの開始

経理代行業務の
開始