2026.01.30
副業時代に経営者が知っておくべき税務知識と「副業300万円問題」の最新動向
2017(平成29)年の「働き方改革実行計画」で副業・兼業の促進が明確に示されて以来、柔軟な働き方がしやすい環境整備の一環として、副業を認める会社は増加しています。そのため、経営者にとっても、副業…
人手不足や物価高などの厳しい情勢が続く中、中小企業が成長を続けるためには、業務改善が欠かせません。東京商工会議所が2024年に実施した「中小企業の経営課題に関するアンケート」によれば、2020年以降に省力化・業務効率化に取り組んだ中小企業は約80%にのぼります。
しかし、「業務改善は効果がなかった」という企業も少なくありません。改善が一時的な取り組みで終わってしまう背景には、次のような共通の課題が存在します。
業務改善を行うにあたって、明確な目的や具体的な目標が設定されていないことがあります。目標設定が曖昧では、業務改善を定着させるのは困難です。
目的がわからないまま「取り組もう」と言われても、社員はどこを目指して何を改善するのか、進むべき方向がわかりません。また、具体的な目標がないと対策が場当たり的になるうえ、改善の効果があるのかどうかもわからないため、モチベーションが低下します。
経営陣が意欲的なケースでは、現場とのギャップが問題になる場合があります。業務改善に取り組む際は、上層部が現場の状況を正確に把握し、実情に即した指示を出すことが不可欠です。現場の声を聞かず、一方的な改善指示を押しつけることになっては、現場の反発を招きかねません。
トップダウンの改善指示は、適切に行えば高い推進力を発揮します。しかし、社員が「やらされている」と感じる環境では、改善させることは難しいでしょう。
業務改善を進める際は、現場の判断に任せることも大切です。しかし、定期的な進捗確認がなければ、現場の取り組みに効果があるのか、企業全体にどのくらい貢献しているのかわかりません。
また、フィードバックがなければ、進捗や現況に合わせた修正や調整もできないでしょう。反応がなければモチベーションは低下し、改善を行う意味を見失って自然消滅へと向かう可能性が高まります。
業務改善の成果が数字に表れるまでには、通常、ある程度の時間がかかります。しかし、改善がうまくいかない企業の多くは、短期間で目に見える効果を求めすぎる傾向があります。
過度な期待はプレッシャーとなり、現場の疲弊を招き、計画の頓挫につながります。また、初期段階で明らかな変化が表れないことから「効果がない」と判断し、早々に打ち切ってしまうケースもあるでしょう。
東京商工会議所が2024年に実施した「中小企業の経営課題に関するアンケート」では、省力化や業務効率化に取り組む際の課題についても調査しています。その結果、「人手不足」と回答した企業が約42%と最も多く、人的課題以外では「資金不足」の約24%が最多であることがわかりました。
リソースに余裕がない中小企業では、社員が日常業務に追われ、改善に手が回らないことが考えられます。また、予算が続かずに諦めざるを得ないケースもあるでしょう。
業務改善が定着しない理由は企業によって異なるため、自社にとっての「続かない理由」を明らかにして対策を講じましょう。
ただし、前提として、業務改善は社員全員が「自分ごと」として捉え、主体性を持って取り組むことが重要です。「自分ごと」である意識が、日々の取り組みを継続させ、企業全体を引き上げる力になります。そのために必要な工夫と具体的なヒントを5つ紹介します。
全社員が関わる業務改善には、社員自身が選択し、自発的に参加できる方法を取り入れると効果的です。例えば、参加者が自由にアイデアを出し合うブレインストーミングや、意見を交わして結論を出すグループディスカッションなどのワークショップは、社員が業務改善を「自分ごと」として捉えるのに役立ちます。
また、業務改善プロジェクトに、実行責任者であるリーダーとは別にアンバサダーを置く方法も良いでしょう。アンバサダーは、社内のコミュニケーションツールなどを通じてプロジェクトのメリットやベネフィットを広め、社員への定期的なアンケートや意見ボードの設置などを実施して、現場の声を積極的に吸い上げます。プロジェクトと社員をつなぐ役割を担うアンバサダーの効果で、プロジェクトの推進と周知が行いやすくなります。
業務改善に取り組む際には、明確で実現可能な目標を設定することが重要です。特にSMART目標(Specific:具体的な、Measurable:測定可能な、Achievable:達成可能な、Relevant:関連する、Time-bound:期限を定めた)を活用することで、より効果的な目標設定が可能になります。
このフレームワークを用いることで、例えば「2026年4月に入社する新卒社員の1年後の離職率を、現状の15%から10%に引き下げる」といった具体的かつ測定可能な目標を設定できるでしょう。
達成すべきゴールを設定した後は、そこへ至る道筋として、タスクを細分化したスモールステップと大きな目標であるビッグステップを設定することが重要です。
スモールステップは、達成しやすい小さな目標をコツコツと積み重ねていくことで、社員がモチベーションを維持しながら着実にゴールを目指せる仕組みです。進捗が目に見えることで、取り組みを継続しやすくなります。
一方のビッグステップは、スモールステップを積み重ねた先にある大きな目標として設定するもので、成功すると大きな達成感を得られます。ただし、現実とかけ離れた目標にすると、現状とのギャップからモチベーションの低下や挫折を招くおそれがあるため、注意が必要です。
スモールステップとビッグステップを適切に組み合わせることで、ゴール達成の実現可能なプロセスが明確になり、社員の主体的な関与を促します。
業務改善を継続するためには、日常業務に組み込むと良いでしょう。社員が業務改善の効果を具体的に実感することで、「自分ごと」として捉えやすくなります。
日常業務に組み込むためには、改善項目のリスト化や手順のマニュアル化を行い、業務の一部として定着させることが重要です。また、すでに毎日朝礼を行っている企業では、朝礼時に1分間の振り返り時間を設けることも有効です。社員に新たな負担をかけることなく、改善活動を習慣化できます。
プロジェクトの進捗確認やフィードバックは、現況を把握し適切な軌道修正を行うためにも不可欠です。
進捗管理には、ガントチャートやカンバンボードといったプロジェクト・タスク管理ツールの導入が有効です。スモールステップ・ビッグステップの達成率や現況などの進捗情報が可視化され、全社員に共有できます。
また、週次や月次で短時間のミーティングを行い、進捗報告の場を設けることで、問題点を確認し、計画のこまめな修正が行えます。スモールステップ達成の評価やフィードバックの場としても有効で、モチベーション維持に役立つでしょう。
「○○週間」「○○強化月間」のように業務改善をイベントとして扱っている企業では、期間の終了と同時に改善活動をやめてしまうケースが少なくありません。これでは、取り組みが定着しないどころか、取り組み前の状態に戻ってしまう可能性が高いでしょう。
業務改善は特別なイベントではなく、「日常的な業務の一部」として扱うことが大切です。そのためには、無理のない計画を立て、小さな活動を積み重ねることで習慣化につながります。気がつけば、それを実践することが当たり前になっているでしょう。
業務改善を成功させるためには、社員全員が「自分ごと」として主体的に取り組むことが重要です。それは「自社だけで完結させる」という意味ではありません。専門的なノウハウが不足している状態で独自に進めると、リソースの浪費や企業の疲弊につながる可能性があります。
効率的な業務改善を実施するためには、外部のプロにDX導入のサポートを依頼することが有効です。経験豊かな専門家の視点を取り入れることで、自社の状況に合った計画の立案と、最適なツール導入が可能となります。これにより、無理のない業務活動が継続でき、長期的な成果を得ることができるでしょう。
DX導入については、下記コラムで詳しく解説しています。
業務効率化のメリットを増やすには「クラウドツール導入サポート」の利用が◎
神奈川 横浜・町田経理アウトソーシングオフィスは、経理・税務・経営に関するお客様のあらゆる課題を解決する総合会計事務所です。創業50年以上の歴史を持ち、約100名の専門家がお客様の事業を力強くサポートします。
約100名体制の経理・税務・経営のプロフェッショナルが、お客様の状況に合わせた最適なソリューションを提供します。複雑な課題も多角的な視点から解決に導き、お客様の成長を強力に後押しします。
会計・経理業務から給与計算、各種コンサルティングまで、DX化推進とアウトソーシングを支援します。これにより、お客様は本業に集中でき、業務の効率化と人件費などのコスト削減を同時に実現します。
最新のクラウド会計システムを積極的に活用し、経営数値のリアルタイムな把握を可能にします。これにより、迅速な経営判断をサポートし、事業の成長を加速させます。
経理・税務の基本サポートに加え、会社設立、相続、さらには医療機関や社会福祉法人に特化した専門的なコンサルティングも提供します。お客様の事業フェーズや業界に合わせたきめ細やかなサポートが可能です。
バックオフィスの改善や、経理・労務、経営に関するお悩みを信頼できる専門集団に任せたい経営者の方は、ぜひお問い合わせください。



経理体制の
ヒアリング(無料)

貴社の課題解決の
ためのご提案

ご契約
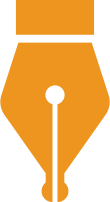
貴社の業務フローの
改善サポートの開始

経理代行業務の
開始