2025.12.28
請求ミスを防ぐ業務フロー整備の実践ポイント
中小企業に多い「1人経理」は、属人化や担当者の業務過多によってミスが多発するリスクがあります。特に、請求処理に関わるミスは、売上の回収遅延や損失だけでなく、取引先の信頼を失うことにもなりかねません。 …
電子帳簿保存法って何?2025年対応版、経理が知っておきたい基礎知識
2023年末の猶予期間終了により、電子帳簿保存法(電帳法)への本格対応が必須になっております。
対応が義務化されたとはいえ、「電子帳簿保存法って結局どう対応すればいいの?」「自社にはどこまで関係あるのか分からない」と悩む経理担当者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、2025年現在の最新の電子帳簿保存法の概要とポイント、経理担当者がやるべきことをわかりやすく解説していきます。
この記事を読むことで、電子帳簿保存法の基本ルールから、対象となる帳簿・書類の種類、そしてスムーズな対応方法までを一通り理解できます。
中小企業の経営者や経理担当者の皆さまは、ぜひ最後までご覧ください。
電子帳簿保存法(電帳法)とは、国税関係帳簿や書類を電子データで保存する際のルールを定めた法律です。
従来は紙での保存が原則でしたが、デジタル化の推進や業務効率化を目的として、1998年に制定され、その後何度も改正されてきました。
2022年の大幅改正を経て、原則として電子取引のデータは2024年1月から完全義務化され、電子保存が必須になっています。
電子帳簿保存法は、保存対象に応じて以下の3つに区分されます。
特に③の電子取引データ保存が企業にとって重要で、誤った対応をすると青色申告の取り消しなどの重大なペナルティにも繋がりかねません。
電子取引とは、「請求書や見積書などの取引情報を電子的に受け取った・送信した」取引を指します。
具体的には以下のようなケースが該当します。
上記のようなデータは紙に印刷して保存するだけではNGで、要件を満たす電子データとして保存する必要があります。
2025年時点で求められる要件は以下の通りです。
これらの要件を満たさないと、税務調査時に否認されるリスクがあるため、確実な整備が必要です。
電子取引で受け取った書類を紙に印刷して保存しても違法になります。
例えば、メール添付の請求書や、クラウドサービスからダウンロードした領収書などは、電子で保存しなければならないと明記されています。
多くの中小企業が同じ悩みを抱えています。対応策としては、
といった方法がありますが、税法の専門家である会計事務所や税理士に相談しながら進めることが最も安心かと思います。
電帳法では、検索機能として以下の3項目が求められています。
これらでファイル検索できるようにしておく必要があります。ファイル名に情報を含める、スプレッドシートで台帳を作る、対応ソフトを使うなどの方法が有効です。
電子化対応には手間もありますが、長期的に見ると以下のようなメリットがあります。
一方で、電子帳簿保存法対応にあたって以下の点には注意が必要です。
「とりあえず印刷しておこう」では通用しないため、社内ルールの明文化と継続的な運用体制の整備が求められます。
2024年から電子帳簿保存法の完全対応が求められ、すべての企業が電子取引データの電子保存義務を負うことになります。
特に中小企業では、「どこまで対応すればいいのか分からない」と悩むケースも多いですが、正しい知識とステップを踏めばスムーズに移行可能です。



経理体制の
ヒアリング(無料)

貴社の課題解決の
ためのご提案

ご契約
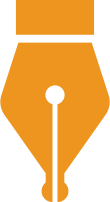
貴社の業務フローの
改善サポートの開始

経理代行業務の
開始