2025.12.28
請求ミスを防ぐ業務フロー整備の実践ポイント
中小企業に多い「1人経理」は、属人化や担当者の業務過多によってミスが多発するリスクがあります。特に、請求処理に関わるミスは、売上の回収遅延や損失だけでなく、取引先の信頼を失うことにもなりかねません。 …
2025年10月1日に施行される育児・介護休業法の改正は、中小企業にとって「柔軟な働き方」への対応を本格化させる重要な転換点です。しかし、リソースが限られている中小企業にかかる負担は大きく、法令遵守と業務効率の両立が難しいのが実情でしょう。
そこで本コラムでは、育児・介護休業法改正の概要を紹介し、中小企業における課題と解決に向けた対策を詳しく解説します。
≪目次≫
育児・介護休業法は、正式名称を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といいます。その名の通り、育児や介護を担う労働者が、仕事と家庭を両立できるように支援するための法律です。1992年の施行以来、育児や介護を取り巻く社会環境の変化に応じて、改正を繰り返しています。
なかでも、2025年の大改正では11もの項目が改正や拡充の対象となり、4月と10月に分けて段階的に施行されることとなりました。
まず、中小企業にも影響が大きい主な制度を整理しておきましょう。
育児・介護休業法における主な制度は以下の通りです。育児休業制度は子育て中の労働者、介護休業法では要介護状態の家族を介護する労働者を対象としており、どちらも労働者の性別は問いません。すべての企業に、円滑な運用に向けた社内整備を行う義務があります。
【育児に関する主な制度】
・育児休業:出産から子が1歳(最長2歳)まで、子ども1人につき2回まで取得可能
・子の看護休暇:未就学児の看護に時間単位で取得可能(子ども1人:年5日まで、2人以上:年10日まで)
・所定外労働の制限・短時間勤務制度:3歳未満の子どもがいる場合、残業免除・勤務時間短縮が可能
・深夜業の制限:未就学児がいる場合、午後10時から午前5時までの労働を免除
【介護に関する主な制度】
・介護休業:要介護家族1人につき3回まで、通算93日まで取得可能
・介護休暇:対象家族が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日まで、時間単位で取得可能
・所定外労働・時間外労働の制限:介護終了まで、残業に制限を設けることができる
・深夜業の制限:介護終了まで、午後10時から午前5時までの労働を免除
・短時間勤務等:事業主は短時間勤務・フレックスタイム・時差出勤・介護費用助成のいずれかを講じる
今回の改正に先駆けて、2025年4月には以下の制度拡充が実施されました。
【育児に関する制度拡充】
・子の看護休暇の見直し:対象者の継続雇用期間制限を撤廃、子どもの年齢を引き上げ(小3まで)、取得理由に学級閉鎖や園行事を追加
・残業免除の対象拡大:子どもの年齢を小学校就学前までに拡大
【介護に関する制度拡充】
・介護休暇の取得要件緩和:勤続条件を撤廃
・介護離職防止措置の導入義務:事業主は介護支援に関する研修・相談窓口・事例提供等のいずれか実施
・個別の周知・意向確認の強化:制度説明&40歳到達時の情報提供が義務化
【育児・介護に共通する努力義務としての拡充】
・テレワークの導入:努力義務3歳未満の子どもがいる場合や「短時間勤務」制度の代替措置、介護を行う労働者の選択肢として、テレワークを導入する
続いて10月施行分の改正では、育児と仕事の両立支援に関して、事業者に法的義務が生じる項目が増えることになりました。具体的な内容については、以下の通りです。
事業主は、3歳から小学校就学前の子どもを養育する労働者に対して、「始業時刻等の変更・テレワーク(10日以上/月)・保育施設の設置・養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)・短時間勤務制度」のうち、2つ以上を用意しなければなりません。
事業主は、3歳未満の子どもを持つ従業員に対して、自社の「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」について説明する機会を設ける必要があります。このとき、対象制度の説明と意向確認を、個別に実施することが重要です。また、家庭や仕事の状況が変化することを踏まえ、定期的な面談を行うことが望ましいとされています。
事業主は、3歳未満の子どもを持つ従業員に対して、意向確認の場を個別に設ける義務が生じます。これは、両立支援制度の利用期間や条件を、事業主と労働者がすり合わせるために重要です。また、ここで聴取した意向に基づき、自社の状況に応じた配慮をしなければなりません。
このように、2025年の改正では、テレワークをはじめとする「柔軟な働き方」への対応強化が求められます。しかし、テレワークの導入は、単に「在宅勤務を許可する」だけでは成立しません。就業規則の見直しを含む業務体制の再構築が必要です。特に、以下の課題を抱える企業では、業務のデジタル化、情報共有の仕組みづくりといった、根本的な業務改革が急務となります。
経理や総務などのバックオフィス業務に、紙文化が根強く残っているケースも少なくないでしょう。原本の確認や押印といった物理的なやり取りは、出社での対応を前提としています。テレワークをスムーズに行うためには、業務のデジタル化が不可欠です。まず、クラウド型ワークフローや電子決裁の導入によるペーパーレス化を推進する必要があります。
経理業務は専門性が高く、担当者への依存度が大きいのが特徴です。特に中小企業では、経理・総務・労務などのバックオフィス業務を担う「1人経理」が多く、属人化が加速する傾向があります。属人化した業務では、担当者の不在が業務停滞に直結し、企業全体の業務低下を招きかねません。ボトルネックを作らないためにも、属人化対策が必要です。
改正後の制度運用では、従業員ごとの意向確認や勤務時間の調整、テレワーク配慮など、多くの場面で個別対応が求められます。これにより管理工数が増え、管理者負担も増加します。またこうした状況における専任者のいないケースでの課題は、兼任者や経営者が対応せざるを得ず、コア業務に集中が妨げられることです。こうした煩雑さを軽減するためには、制度運用の仕組み・ルールの整備が鍵となります。
従来のタイムカードに打刻する勤怠管理では、出社せずに働くテレワークに対応しきれません。また、時短勤務や育児・介護休暇の時間制取得など個別の申請が増えることで、管理業務はさらに複雑化します。労働時間を正確に把握し、間違いのない給与計算を行うためには、勤怠管理方法を見直すことも重要です。
従来の会計管理・労務管理は、紙ベースやインストール型ソフトでの運用が多く、柔軟な働き方に対応するには限界があります。そこで、クラウド型システムに移行することで、テレワーク環境整備と業務効率化が実現可能です。業務のデジタル化、属人化の解消、業務効率化など、先に挙げた4つの課題解決も望めます。
ここからは、具体的な効果について、1つずつ解説しましょう。
クラウド型システムでは、データがインターネット上のクラウドサーバーに保存されるため、複数の従業員が同時に同じデータにアクセス可能です。業務担当者だけでなく、経営者や他部門の従業員との情報共有が容易になり、効率的な一元管理が実現します。これにより、以下の効果が期待できます。
業務に必要なデータはすべてクラウド上で管理されているため、テレワークのために資料を持ち帰る必要はありません。また、作業はリアルタイムでシステムに反映されるため、成果物を提出するための出社も不要です。これにより、育児・介護を抱える従業員のテレワークを実現し、急な状況変化にも対応しやすくなります。
クラウド上のデータは、経営者や他部門の従業員も閲覧できるため、担当者不在による業務停滞を回避が見込めます。業務計画の立案やプレゼン資料等に経理データを必要とするケースに、効果的です。また、顧客対応、資金調達、税務調査など、必要なタイミングで必要な情報を得ることができるため、経営判断の迅速化にも役立ちます。
アクセス権限を持つ従業員はIDによって管理され、アクセス履歴や操作ログはすべて自動的に記録されます。不正やミスが発生した場合でも、ログ情報をもとに迅速な原因特定と対応が可能です。記録が残る環境下では従業員の意識も高まり、不正の抑止効果が期待できます。また、操作履歴の可視化は進捗把握にも有効です。テレワーク環境下の「仕事の様子が見えない」といった不安を払拭し、管理者と作業担当者の信頼関係構築にも貢献します。
クラウド型会計システムは、既存システムとの連携やオプションの追加で、会計業務以外も一元管理できるのが強みです。これにより、社内全体のDXが進み、作業環境の改善が行えます。
勤怠管理や給与計算システムと連携することで、出退勤記録の取得から給与計算、税額の算出までを一貫して自動化できます。時間単位の休暇取得や時短勤務の計算にも柔軟に対応でき、法令改正に則した処理への切替もスムーズです。さらに、年末調整では、従業員自身が必要な情報をシステム上で直接登録する方法が選択でき、大幅な工数削減とペーパーレス化促進を実現します。
ワークフロー機能のあるクラウドツールや承認システムをクラウド上で連携させることで、紙ベースの決裁から脱却し、物理的な書類回付や押印の手間を省けます。これにより、時間や場所に縛られない意思決定が可能となり、テレワークやフレックス勤務にも柔軟に対応可能です。決済履歴が自動的に記録されるため、監査対応や内部統制の強化にも寄与します。
育児・介護などの事情により、休業の延長や退職が発生する可能性は否定できません。クラウド型会計システムを活用することで、業務属人化を防ぎ、引き継ぎしやすい環境整備にも役立ちます。これにより、業務停滞や情報の断絶を防ぎ、企業活動の安定性が高まるでしょう。
特定の担当者に依存したまま退職が発生すると、業務フローがブラックボックス化し、解析や再構築に大変な労力が必要です。しかし、クラウド型会計システム上の活用で、業務手順が明確に記録されます。業務フローの可視化によって業務の標準化が進み、属人化リスク低減にもつながります。
業務フローの可視化は、二度手間や作業の重複を排除し、最適化を図る際にも効果的です。また、複数人による業務分担がしやすく、急な欠員があった場合にも既存リソースで対応できる環境が整います。
クラウド型会計システムでは、銀行などの金融機関、販売店のPOSレジシステム、法人クレジットカードや交通系ICカードとの連携が可能です。こうすることで、取引データの取得から仕訳記帳、集計までを自動化できます。
自動仕訳や自動集計機能により、転記漏れや計算ミスといったヒューマンエラーが防げます。また、自動化により意図的な改ざんを行う余地もありません。システムに搭載されたAIと担当者・管理者によるダブルチェック体制が整い、経理データの精度が大きく向上します。
相次ぐ法改正にも、運営元による自動アップデートで適切に対応可能です。もちろん、育児休業制度の改正にも適宜アップデートが実行され、適切なタイミングで移行します。今後の法改正にも、自社で備える必要はありません。
作業履歴の記録により、税務調査や監査対応があっても速やかに対応できます。さらに、提携税理士と直接システム画面を共有すれば、オンライン相談やオンライン監査も可能です。実際の管理画面を見ながら話せるため、より適切なアドバイスが受けられるでしょう。
クラウド型システムの導入により、経費・人件費・売上などの実績がクラウド上に蓄積されます。これらのデータを一元管理することで、部門別・時期別の傾向分析など、多角的なデータ分析が行いやすくなります。このように、経営判断の材料を定量的に把握できるのもクラウド型システム活用の強みです。
多様な働き方への対応については、下記記事でも詳しく解説しています。
https://keiri-outsourcing.com/column/column-8712/
「多様な働き方」にはどの方法で対応すべきか
育児・介護休業法の改正への対応は、環境整備のための時間やコストがかかり、中小企業にとっては大きな負担となるでしょう。しかし、視点を変えれば「DXによる働き方改革の好機」だと考えることもできます。
クラウド型会計システムの導入は、バックオフィス業務からDXを推進し、業務効率化と柔軟な勤務体制構築の両立を可能にします。
どのように進めるべきかお悩みでしたら、ぜひ、弊社にご相談ください。
弊社では、専門家による丁寧なヒアリングを実施し、貴社に最適なシステム選定から導入サポートまでを一貫して行います。
まずは、無料相談で貴社の課題を一緒に整理してみませんか?
下記フォームより、お気軽にご連絡ください。
神奈川 横浜・町田経理アウトソーシングオフィスは、経理・税務・経営に関するお客様のあらゆる課題を解決する総合会計事務所です。創業50年以上の歴史を持ち、約100名の専門家がお客様の事業を力強くサポートします。
約100名体制の経理・税務・経営のプロフェッショナルが、お客様の状況に合わせた最適なソリューションを提供します。複雑な課題も多角的な視点から解決に導き、お客様の成長を強力に後押しします。
会計・経理業務から給与計算、各種コンサルティングまで、DX化推進とアウトソーシングを支援します。これにより、お客様は本業に集中でき、業務の効率化と人件費などのコスト削減を同時に実現します。
最新のクラウド会計システムを積極的に活用し、経営数値のリアルタイムな把握を可能にします。これにより、迅速な経営判断をサポートし、事業の成長を加速させます。
経理・税務の基本サポートに加え、会社設立、相続、さらには医療機関や社会福祉法人に特化した専門的なコンサルティングも提供します。お客様の事業フェーズや業界に合わせたきめ細やかなサポートが可能です。
バックオフィスの改善や、経理・労務、経営に関するお悩みを信頼できる専門集団に任せたい経営者の方は、ぜひお問い合わせください。



経理体制の
ヒアリング(無料)

貴社の課題解決の
ためのご提案

ご契約
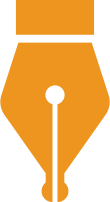
貴社の業務フローの
改善サポートの開始

経理代行業務の
開始