2026.01.30
副業時代に経営者が知っておくべき税務知識と「副業300万円問題」の最新動向
2017(平成29)年の「働き方改革実行計画」で副業・兼業の促進が明確に示されて以来、柔軟な働き方がしやすい環境整備の一環として、副業を認める会社は増加しています。そのため、経営者にとっても、副業…
日々の経理業務で欠かせない「仕訳」。この仕訳に使われる「勘定科目」に苦手意識を持っている新入社員は少なくありません。「どの勘定科目を使えば正しいのか分からない」「なんとなくで使っているけれど合っているか不安…」といった声もよく聞かれます。
このコラムでは、勘定科目の基本的な考え方から、覚えるコツ、実務に活かすためのポイントまで、わかりやすく解説していきます。記事の最後には、経理担当者が新人教育の中で意識すべきポイントについても紹介しています。
この記事を読むと、勘定科目の「なぜそうなるのか」が理解でき、仕訳に対する苦手意識が減り、ミスの少ない安定した経理業務につながるはずです。新入社員の教育を担当する経理部門の方、仕訳の基本を今一度整理したい経理担当者は、ぜひ最後までご覧ください。
勘定科目とは、会社のすべての取引を記録・整理するための「分類名」です。たとえば「文房具を購入した」なら「消耗品費」、「現金を受け取った」なら「現金」や「売掛金」などが該当します。
仕訳とは、この取引を「借方」と「貸方」に分けて記録する作業。仕訳を行うには、取引の内容に応じて適切な勘定科目を選ぶ必要があります。
取引内容をどのグループに当てはめるかを理解しておくと、勘定科目を選ぶときに迷いが減ります。
例えば、同じようにお金を支払う取引でも、「消耗品費」「事務用品費」「雑費」など、どの勘定科目にすべきか迷うケースが多くあります。実際、明確なルールが会社によって異なる場合もあるため、新人が混乱するのは当然です。
そのため、会社ごとに定められた「勘定科目ルールブック(勘定科目の使い分け表)」を共有することが大切です。教育担当者は新人が迷ったときにすぐ確認できるような一覧表を用意しておくとよいでしょう。
勘定科目に迷ったときは、「何に対して、どこからお金が動いたのか?」を考えてみましょう。
たとえば「携帯電話料金をクレジットカードで支払った」なら、
という風に、取引の実態に即して仕訳ができるようになります。
解説:会社の手元にある現金を指します。小口現金も含まれます。
使用場面:社員が立て替えた交通費を現金で精算した/現金売上があった。
注意点:現金残高と実際の金庫内現金は常に一致している必要があります。
解説:会社名義の銀行口座の残高や入出金を記録します。
使用場面:売上の入金、給与の振込など。
注意点:通帳残高と帳簿残高の定期照合が必要。
解説:商品やサービスを提供したが、まだ代金を受け取っていない場合に使用。
使用場面:納品後・請求済みで未入金。
注意点:入金管理を徹底し、滞留債権を防ぎましょう。
解説:商品やサービスを仕入れたが未払いの場合に使用。
注意点:買掛金の支払い漏れ防止、「未払金」との区別に注意。
解説:出張や営業活動で発生した交通費や宿泊費を処理。
注意点:レシート保管必須。通勤費は「福利厚生費」扱いの場合あり。
解説:電話代・インターネット回線・郵便代など通信コスト。
注意点:切手代・クラウド利用料の処理区分に注意。
解説:少額・短期利用の文房具や備品に使用。
注意点:高額・長期利用の物品は資産計上。
解説:電気・水道・ガスなどのインフラコスト。
注意点:家事按分が必要な場合あり。請求書保存を徹底。
解説:振込・決済代行などの手数料を処理。
注意点:交際費・雑費との仕分けミスに注意。
解説:他の科目に該当しない一時的費用。
注意点:頻繁に使用しない。社内基準を設ける。
実際の取引をイメージして覚えると定着しやすくなります。
科目の判断にはグレーゾーンがあり、会社方針で異なる場合もあります。
日々の実務とセットで勘定科目を学ばせることが最も効果的です。
仕訳と勘定科目の理解は経理の基本であり、取引の「意味」を読み解くための重要なツールです。「なぜその科目を使うのか」を意識することで、実務力が大幅に向上します。
新入社員を指導する際は、「分類」「お金の流れ」「判断の根拠」を意識させながら段階的に教育しましょう。
弊社では、経理業務の新人教育に特化した研修や、実務で使える勘定科目マニュアルのご提供も行っております。経理体制の強化を検討されている企業様は、ぜひ一度ご相談ください。



経理体制の
ヒアリング(無料)

貴社の課題解決の
ためのご提案

ご契約
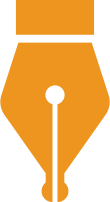
貴社の業務フローの
改善サポートの開始

経理代行業務の
開始