2025.12.28
請求ミスを防ぐ業務フロー整備の実践ポイント
中小企業に多い「1人経理」は、属人化や担当者の業務過多によってミスが多発するリスクがあります。特に、請求処理に関わるミスは、売上の回収遅延や損失だけでなく、取引先の信頼を失うことにもなりかねません。 …
賞与にかかる社会保険と税金、知らないと損する処理の基本
企業の皆さま、こんにちは。
毎年、夏や冬に支給される賞与(ボーナス)は、社員のモチベーションを高める大きな手段です。しかし、賞与を支給する際には社会保険料や税金の処理が通常の給与とは異なるため、正しく理解していないと余計なコストやトラブルを招く恐れがあります。
「賞与にも社会保険料ってかかるの?」「税金の計算って給与と同じ?」「処理を間違えたらどうなる?」と不安に感じている中小企業の経営者や経理担当者も多いのではないでしょうか。
この記事では、賞与にかかる社会保険や税金の基本的な仕組みから、損をしないための具体的な処理方法までをわかりやすく解説します。
この記事を読むことで、以下のような疑問が解消できます:
賞与を正しく処理して、社員にも会社にもメリットを生みたい中小企業の経営者・経理担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。
賞与(ボーナス)にも、給与と同様に社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)や所得税がかかります。
よくある誤解として、「賞与は臨時収入だから保険料がかからない」と思われがちですが、これは間違いです。
賞与は国の制度上、「報酬」として扱われるため、通常の給与と同様に課税対象になります。つまり、税金や保険料の処理を怠ると、あとから追徴やペナルティを受けるリスクがあるのです。
賞与に対する健康保険・厚生年金の保険料は、「標準賞与額 × 保険料率」で計算します。
標準賞与額とは?
実際の賞与支給額をベースにしますが、1回あたり150万円が上限とされています。例えば、200万円の賞与を支給しても、150万円を上限として保険料を計算します。
保険料の計算例(東京都・協会けんぽ加入企業の場合)
健康保険料:80万円 × 10.00% = 80,000円
厚生年金保険料:80万円 × 18.30% = 146,400円(※労使折半)
このうち半分は会社負担、半分は本人負担となります。
雇用保険も賞与に対して課されます。料率は年度ごとに変動しますが、令和6年度は以下の通り(一般の事業の場合)です。
賞与にかかる雇用保険料も、給与と同様に源泉徴収し、納付が必要です。
給与と異なり、賞与の所得税は以下の2ステップで計算されます。
例)
扶養家族の数が1人で、前月給与が30万円の場合、算出率は約3.06%。
→ 80万円の賞与 × 3.06% = 24,480円
※注意:住民税は原則として賞与からは引かれず、毎月均等に天引きされます。
賞与支給後、5日以内に「賞与支払届」を年金事務所または電子申請で提出する必要があります。これを忘れると、社会保険料が未納となり、事後的な手続きが煩雑になります。
賞与の源泉税は概算です。年末調整時に過不足が調整されますが、賞与を複数回支給する企業は累積額を意識した源泉徴収が重要になります。
給与計算ソフトやクラウド会計を導入している企業でも、設定ミスや更新漏れがあると誤った処理がされます。支給前に必ず人の目で確認しましょう。
社会保険料は月単位での支給額に対してかかるため、例えば「6月と7月に分割支給」することで月ごとの保険料負担を抑えることが可能です(上限に達している場合)。
現金の賞与ではなく、非課税となる手当(通勤手当、出張旅費等)を活用する、福利厚生としての支援に切り替えることで、社員の手取り額を維持しつつ会社側のコストも抑えられます。
賞与の支給に際しては、社会保険料や税金の正確な処理が非常に重要です。給与と同様の感覚で処理してしまうと、誤徴収や未納などのリスクが発生し、会社と社員双方に損失をもたらしかねません。
しかし、ポイントを押さえて適切に処理することで、余計なコストを抑え、社員満足度の向上にもつなげることが可能です。
特に中小企業では、経理担当者が少人数で業務を担っていることが多いため、ミスを防ぐためにも、給与・賞与処理のマニュアル化やクラウドシステムの活用も効果的です。
弊社では、賞与の支給・計算・社会保険対応を含めた給与計算アウトソーシングにも対応しています。
複雑な税務・労務処理も、経験豊富なスタッフがサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。



経理体制の
ヒアリング(無料)

貴社の課題解決の
ためのご提案

ご契約
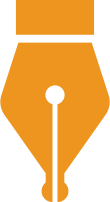
貴社の業務フローの
改善サポートの開始

経理代行業務の
開始