2025.12.28
請求ミスを防ぐ業務フロー整備の実践ポイント
中小企業に多い「1人経理」は、属人化や担当者の業務過多によってミスが多発するリスクがあります。特に、請求処理に関わるミスは、売上の回収遅延や損失だけでなく、取引先の信頼を失うことにもなりかねません。 …
退職時に必要な社会保険・税金関連の手続きを一気に確認!
退職が決まると、仕事の引継ぎや挨拶回りなどであっという間に時間が過ぎていきます。しかし、忘れてはならないのが「社会保険」と「税金」に関する手続きです。これらの手続きを怠ると、あとから高額な請求が届いたり、必要な保障が受けられなかったりするケースがあります。
この記事では、退職時に必要な社会保険・税金の手続きをすべて網羅し、どのような順序で対応すべきか分かりやすく解説します。退職を控える中小企業の経営者や経理担当者の方は、社員のサポートに活用してください。
退職時には、主に以下の2つの分野で手続きが必要です。
それぞれに期限や注意点があるため、ポイントを押さえたうえで進めることが重要です。
退職後は会社の健康保険が使えなくなります。以下のいずれかを選ぶ必要があります。
それぞれの特徴と注意点を解説していきます。
退職すると厚生年金の加入資格がなくなります。国民年金への切り替えが必要です。
収入が一時的に減少する場合、保険料の免除や納付猶予制度を利用できます。申請しないと未納扱いになるため注意が必要です。
たとえ退職して無職になっても、前年の所得に対する住民税は支払う必要があります。
退職から時間が経って請求が届くため、見落とさないよう注意が必要です。
確定申告をすることで、払いすぎた税金の還付が受けられる可能性があります。特に以下は確認しましょう。
退職者が転職や失業手当の申請に必要とする場合があります。速やかに発行できるよう準備しておきましょう。
※自己都合退職の場合、すぐには支給されない点に注意が必要です。
| 手続き項目 | 手続き先 | 期限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 健康保険(任意継続) | 協会けんぽ等 | 退職後20日以内 | 全額自己負担 |
| 国民健康保険加入 | 市区町村 | 退職後14日以内 | 所得に応じて保険料決定 |
| 国民年金切り替え | 市区町村 | 退職後14日以内 | 免除申請も可能 |
| 住民税 | 市区町村 | 納付書到着後 | 普通徴収・一括徴収の確認要 |
| 所得税(確定申告) | 税務署 | 翌年2〜3月 | 年末調整がない場合 |
| 失業手当 | ハローワーク | 離職後すぐ | 離職票の入手が必要 |
退職時には、健康保険・年金・税金・雇用保険と、さまざまな公的手続きが必要です。これらの手続きを怠ると、保障を受けられないなど、思わぬ出費が発生する恐れがあります。
中小企業においては、経理担当者や経営者がこうした手続きをしっかり把握し、社員が安心して退職できる体制を整えることが重要です。
当事務所では、退職者対応における社会保険・税務手続きのアドバイスや、実務サポートも承っております。煩雑な手続きをまるごとアウトソーシングしたい場合も、お気軽にご相談ください。



経理体制の
ヒアリング(無料)

貴社の課題解決の
ためのご提案

ご契約
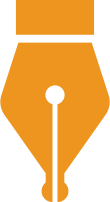
貴社の業務フローの
改善サポートの開始

経理代行業務の
開始