2025.12.28
請求ミスを防ぐ業務フロー整備の実践ポイント
中小企業に多い「1人経理」は、属人化や担当者の業務過多によってミスが多発するリスクがあります。特に、請求処理に関わるミスは、売上の回収遅延や損失だけでなく、取引先の信頼を失うことにもなりかねません。 …
中小企業では、ベテラン社員の経験や勘に依存した「暗黙知」が属人化を加速させてしまうことが少なくありません。暗黙知が蓄積したままだと、ベテラン社員の高齢化や退職によってノウハウが失われ、業務停滞や人材育成の遅れを招くことになるでしょう。本コラムでは、暗黙知を形式知へと変換し、組織資産として活用するための方法を解説します。
≪目次≫
暗黙知とは、言葉や文書では説明しきれない、個人の経験や直感に基づいて形成された知識やノウハウのことをいいます。身近な例として、熟練の職人が持つ技術的な「勘」や、ベテラン社員が培った顧客対応の「コツ」などが挙げられます。
一方、形式知とは、文章や図表などで明示できる知識のことです。企業の持続的な成長を促すためには、暗黙知をいかに形式知に変換し、共有していくかが重要な鍵になります。
中小企業には、「暗黙知が生まれやすく、放置されやすい」という課題があります。貴重な知見が特定の個人にとどまり、組織全体に共有されないまま失われていく状況は、企業にとって大きな損失です。
なぜ、中小企業では暗黙知の活用が進みにくいのでしょうか。そこには、主に3つの理由があります。
少数精鋭の中小企業では、特定の社員が長期間同じ業務を担当するケースが珍しくありません。「わからないことは、あの人に聞けば解決する」といった状況が常態化し、暗黙知を組織的に共有する必要性が見えにくくなってしまいます。
中小企業では、それぞれの担当業務幅が広く、1人の社員が複数の業務知見を抱えています。しかし、日々の業務に追われる中で、知識の整理や共有に時間的な余裕はありません。結果として、暗黙知が特定の個人に蓄積されたまま、未整理の状態で放置されてしまうのです。
経験知とは、経験から得たコツや勘、状況判断力などを指します。このような経験に根ざしたノウハウは、言語化して他者に伝えることが困難です。リソースが限られている中小企業では、マニュアル作成や研修制度の整備にかかるコストと時間がネックとなるでしょう。
先に述べた通り、中小企業では現場で培った個人の暗黙知が、共有されないまま放置される傾向があります。こうして暗黙知が埋もれてしまうと、どのような問題があるのでしょうか。
ここからは、企業経営に悪影響を及ぼす3つのリスクについて解説します。
暗黙知に依存する業務は属人化が進み、特定の社員しか対応できない状況に陥ります。担当者が急な休職や退職などで不在になると、業務は即座に停滞し、組織の生産性低下や取引先との関係悪化にもつながるでしょう。暗黙知が共有されていない状態は、短期的に見ても大きなリスクとなります。
暗黙知を形式知化する仕組みが整備されていない組織では、業務プロセスの標準化や効率化が難しくなります。これは、長期的な視点でも深刻なリスクです。具体的には、次のような問題が発生し、事業継続に支障をきたす恐れがあります。
担当者の急な不在によるリスクについては、下記コラムでも詳しく解説しています。
「うちの経理は大丈夫」 突然退職する1人経理のリスク
担当者の失敗や試行錯誤を通じて身につけた経験知は、組織にとって貴重な資産です。しかし、暗黙知のまま共有できない環境下では、過去の失敗から学ぶことができずに同じミスを繰り返します。
担当者の知見が暗黙知のまま埋もれていると、業務上の課題や改善点が見えにくく、改革の必要性が認識されません。そうなると、現状維持や従来のやり方に固執する傾向が強まり、挑戦や改革が行われなくなるでしょう。その結果、業務効率化が進まず、企業成長の停滞を招きます。
業務手順やノウハウがマニュアルなどで形式知化されていない場合、新入社員や異動者の教育は、OJT(On-the-Job Training)に頼ることとなります。実地指導には時間やコストがかかるうえ、指導する社員の時間を奪うことにもつながります。
ベテラン社員が過去の失敗や成功から身に付けた教訓や、顧客対応のノウハウなどは、組織にとって重要なものです。しかし、その社員の退職によって、これらの暗黙知も失われます。ベテラン社員の退職が、企業の競争優位性の喪失にもつながるのです。
経理業務は、単なる数字管理ではなく、企業経営の基盤を支える重要な業務です。専門性が高く、知識や技術は短期間で習得できるものではありません。
多くの中小企業では「1人経理」が一般的で、業務の属人化リスクが高まっています。この担当者が休職・退職した場合、企業は経理技能だけでなく、次のようなノウハウや知識を失うことになるでしょう。
取引先によって、支払い条件や請求書フォーマット、対応時に心がけることなどの特徴が異なります。経理担当者は、経験を通してそれぞれのパターンを記憶し、適切に処理するノウハウを積み上げているのです。
社長や役員の決裁パターンや必要書類は、内容に応じて変わります。経理担当者は、優先順位を判断して、適切な資料を準備するコツを身に付けています。
経理業務は、法令遵守が求められる部分を除けば、中小企業ごとの独自ルールで運用されているのが実情です。現場経験を通じて得られる知見は、他社での経験や資格取得では補いきれません。例えば、月次決算の効率的な進め方や、イレギュラーな取引に対する適切な会計処理なども、現場で培われたノウハウです。
企業では、独自の文化や取引慣行に基づく「微妙な判断」が必要な場合があります。これらは、数字だけでは判断できない部分であり、現場経験からくる勘やコツが不可欠です。特に経理業務では、形式的な会計処理だけでなく、個々の背景や事情を踏まえた対応が求められる場面が多く、担当者の経験知が業務品質を左右します。
経理業務には、取引判断や決裁感覚、イレギュラー対応など、定量化しづらい感覚的知識が重要です。こうした暗黙知は属人化しやすく、業務継続や品質安定の面でリスクとなります。
この問題の有効な解決策として、SECIモデルとクラウド型会計システムの活用が挙げられます。これらを組み合わせることによって、経理部門における暗黙知の共有・継承が行いやすくなるでしょう。
SECIモデルは、個人の暗黙知を組織で共有できる形式知に変換し、新たな知識を生み出すためのフレームワークです。共有化→表出化→結合→内面化という4つのステップを循環させることによって、暗黙知を組織の資産へと発展させます。
【個人の暗黙知を暗黙知として共有するステップ】
実際に業務を経験することで、ベテラン担当者が感覚的に蓄積している知識や業務のコツを体得します。現場での直接指導や業務見学などを通して、暗黙知を「共有→共同化」するステップです。
担当者がクラウド型会計システムを操作しながら、その画面を録画します。「なぜ、そのような判断をしたのか」がわかるように、音声記録を併用することが重要です。月次決算や支払い調整などの判断理由を記録することで、客観視や振り返りが容易になります。
【暗黙知を形式知化するステップ】
担当者が経験から得た知識やノウハウなどの暗黙知を、言語化によって形式知に変換するステップです。「どのような場面で、どのような判断をしているか」を明示します。
チャットツールやドキュメントを活用し、会計処理の手順や注意点、処理のポイントなどを整理します。これにより、ベテラン担当者の「コツ」を形式知化して、組織のナレッジとして共有できるようになります。
クラウド型会計システムの機能を使って、アラートや入力ガイド機能を組み込む方法も有効です。例えば「この経費は例外処理あり」などのメッセージを表示することで、ベテラン担当者の判断ポイントを再現できます。
【形式知を組み合わせて組織の形式知を創造するステップ】
バラバラに存在する形式知を整理・統合し、業務マニュアルやテンプレートとして体系的するステップです。これにより、個別の知識を組織で再利用できるようになります。
会計処理パターンを集めて、マニュアルに落とし込みます。タグ管理ができるNotion(https://www.notion.com/ja)などのクラウドツールを活用すると、検索や更新が容易になります。このとき、動画とテキストのマニュアルを結合し、操作方法と判断基準を同じ画面で確認できるようにしておくこともポイントです。
頻出する取引パターンには、テンプレートを用意します。作成したテンプレートは、クラウド上に保存することで共有可能です。これにより、支払い条件や振込対応、税区分などの処理基準を一元化できます。
【形式知を個人の暗黙知に変換するステップ】
形式化された知識やノウハウを、各自が暗黙知として取り入れるステップです。実践を通して、「自分の対応感覚」として習得していきます。
クラウド型会計システムにおける過去の処理事例を用いた実践演習を行います。定期的に、処理内容や判断理由を振り返るミーティングを実施して精度を高めましょう。
クラウド型会計システムの操作履歴を確認すれば、業務習熟度の可視化が可能です。また、指導者が作業内容を確認してコメントを残すことで作業者のレベルに応じた適切なフォローが行えます。
このように、暗黙知の共有や引き継ぎには、クラウド型会計システムが有効です。その理由として、次の3つが挙げられます。
(1)業務履歴が残るため、担当者の暗黙知が記録できる
(2)AIが学習することで、ルール化されていないベテラン担当者の処理傾向も再現可能
(3)画面ごと共有できるため、作業者がつまずいている箇所の把握が容易
クラウド型会計システムの導入は、業務効率化の実現だけでなく、過去に蓄積されたナレッジを活用して、未来の企業成長に生かせる有効な手段です。
ただし、導入効果を最大化するには、自社に適したクラウド型会計システムを選ぶことが重要です。そのためには、プロの視点を取り入れることが大切です。
弊社では、専門知識を有するスタッフによる丁寧なヒアリングによって、貴社に最適なクラウド型会計システムの選定から導入までを一貫してサポートいたします。
初回のご相談は無料で承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
神奈川 横浜・町田経理アウトソーシングオフィスは、経理・税務・経営に関するお客様のあらゆる課題を解決する総合会計事務所です。創業50年以上の歴史を持ち、約100名の専門家がお客様の事業を力強くサポートします。
約100名体制の経理・税務・経営のプロフェッショナルが、お客様の状況に合わせた最適なソリューションを提供します。複雑な課題も多角的な視点から解決に導き、お客様の成長を強力に後押しします。
会計・経理業務から給与計算、各種コンサルティングまで、DX化推進とアウトソーシングを支援します。これにより、お客様は本業に集中でき、業務の効率化と人件費などのコスト削減を同時に実現します。
最新のクラウド会計システムを積極的に活用し、経営数値のリアルタイムな把握を可能にします。これにより、迅速な経営判断をサポートし、事業の成長を加速させます。
経理・税務の基本サポートに加え、会社設立、相続、さらには医療機関や社会福祉法人に特化した専門的なコンサルティングも提供します。お客様の事業フェーズや業界に合わせたきめ細やかなサポートが可能です。
バックオフィスの改善や、経理・労務、経営に関するお悩みを信頼できる専門集団に任せたい経営者の方は、ぜひお問い合わせください。



経理体制の
ヒアリング(無料)

貴社の課題解決の
ためのご提案

ご契約
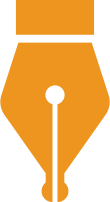
貴社の業務フローの
改善サポートの開始

経理代行業務の
開始