2025.12.28
請求ミスを防ぐ業務フロー整備の実践ポイント
中小企業に多い「1人経理」は、属人化や担当者の業務過多によってミスが多発するリスクがあります。特に、請求処理に関わるミスは、売上の回収遅延や損失だけでなく、取引先の信頼を失うことにもなりかねません。 …
<目次>
かつてサイバー攻撃は、大企業や官公庁が主なターゲットとされていました。しかし、近年では中小企業にもその矛先が向けられています。
特に中小企業では、IT人材の確保やセキュリティ投資が難しく、対策に遅れが生じやすい傾向があります。こうした状況は、サイバー攻撃者にとって“入りやすくドアを開けてくれている状態”と、映りかねません。
身近に迫るサイバー攻撃の脅威を正しく理解し、適切な対策を講じることは、中小企業における重要な課題の1つです。
中小企業がサイバー攻撃に狙われやすい最大の理由は、対策が不十分だからです。ウイルス対策ソフトの導入だけで安心してしまうなど、セキュリティリテラシーの低さが脆弱性を生んでいます。
さらに、取引先に大企業が含まれる場合、中小企業が“踏み台”として利用されるケースも少なくありません。これは、「サプライチェーン攻撃」と呼ばれる手法で、本命である大企業に侵入するための経路として、“侵入しやすい”中小企業が利用されます。自社だけでなく「取引先の情報も預かっている」という認識を持つことが重要です。
中小企業に対するサイバー攻撃が狙うものは、「情報」です。たとえ企業規模が小さくても、以下のような情報は大きな価値を持っています。
中小企業を狙ったサイバー攻撃の手口は年々巧妙化しており、被害の深刻さも増しています。攻撃を受けた企業は、単純に情報を盗まれるだけでなく、金銭的損失や信頼の失墜、業務停止など多角的なダメージを被ることになるでしょう。
ここでは、代表的な手口とそれによって生じる被害の種類を整理します。
サイバー攻撃によるわかりやすい被害が、金銭的損害です。以下のような手口で、企業の資産が失われます。
【例】
このような直接的損失に加え、復旧や社内外対応、機器の買い換えにかかるコスト、関係各所への謝罪・説明コストなどの間接的損失も無視できません。
サイバー攻撃によってシステム障害が発生すると、金銭的損失に加えて業務そのものがストップするリスクがあります。
【例】
奪取された情報が市場に流出することで、企業は重大な責任を問われることになるでしょう。
【例】
企業側のセキュリティ対策が不十分な場合は、サイバー攻撃を受けた被害者でありながら、対策を怠って第三者に損害を広げた加害者と見られることもあるでしょう。その場合、賠償責任や責任追及を受けることがあります。
【例】
サイバー攻撃は、攻撃そのものによる直接的な損害にとどまりません。情報漏えいや営業停止は、企業の信頼性や取引先との関係、経営基盤にまで悪影響をおよぼすリスクがあります。
ここからは、サイバー攻撃の後から拡大しやすい2次被害について説明しましょう。
サイバー攻撃による情報流出や不正アクセスが表面化した場合、企業の社会的信用は大きく揺らぎます。被害を受けたことでリスクが高い企業と見なされ、取引先との契約が打ち切られることもあるでしょう。ブランドイメージは崩れ落ち、マイナス評価から再起を図る覚悟が必要です。
また、セキュリティ対策が甘い企業は従業員からの信用をも失います。退職者が増える一方で、採用活動は難航するでしょう。
マルウエアに感染してシステムが停止した場合、企業活動に大きな遅れが生じます。被害状況によっては復旧作業が長引き、営業機会の損失や顧客離れにつながるかもしれません。
たとえ企業の運営体制が復旧しても取引先や顧客が減少すれば事業の継続は困難となり、企業存続の危機に発展するおそれもあります。
企業のセキュリティ対策に不備があると認められた場合には、以下の法律を根拠とした責任を追及されることがあります。
サイバー攻撃により業務が停滞した場合、他者に損害が発生した場合、法律上保護される利益を侵害した場合などは、経営者が果たすべき善管注意義務違反により賠償の義務を負う
企業の規模や業務内容に応じた適切なセキュリティ体制を整えていない状況下で、サイバー攻撃により企業や第三者に損害が発生した場合、損害賠償責任を負う
クレジットカード番号等取扱契約の締結にかかる業務に対して、番号情報を適切に管理する責任を負う
海外サーバー利用時のデータ管理に不備があった場合は、法的責任が発生する可能性がある
自社のセキュリティ対策不備により情報漏えいを招き、不正アクセスを助長させたと見なされた場合は懲役や罰金などの刑罰が科せられる
このように、できるはずの対策を怠ることは、処罰につながる重大な過失だということを覚えておきましょう。
SECURITY ACTIONとは、中小企業が情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度です。安全・安心なIT社会の実現を目指す独立行政法人・情報処理推進機構(IPA)によって創設されました。
「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」などさまざまな情報がまとめられており、自己診断により必要な取り組みへの過不足を可視化できます。所定の取り組みに応じて「★(一つ星)」「★★(二つ星)」を宣言でき、社内周知や社外アピールにも効果的です。
また、この自己宣言は、一部のデジタル化やサイバーセキュリティ対策に関する公的支援制度の要件にも採用されています。うまく活用することで、対策の一歩を踏み出しやすくなるでしょう。
SECURITYACTIONセキュリティ対策自己宣言
https://www.ipa.go.jp/security/security-action/
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
SECURITY ACTIONでは、すべての企業が最低限取り組むべきセキュリティ対策として、以下の5か条を掲げています。
これらを宣言することで、「★(一つ星)」を使えるようになります。どれも、大きな対策投資を行わなくても、手軽に始められることばかりです。
SECURITY ACTIONが提供する「情報セキュリティ自社診断」をおこなうと、自社のセキュリティレベルを確認できます。チェック内容は以下の通りで、設問数は全部で25問です。
【設問例】
診断結果は、企業ごとの改善ポイントを明確にし、今後の対策立案に役立ちます。設問の意図を解説する文や対策例の紹介もあり、専門知識がなくても理解しやすいでしょう。
次のステップとして「情報セキュリティ基本方針」を策定すると、「★★(二つ星)」を申請できます。
SECURITY ACTIONは中小企業が自ら取り組める対策ですが、それでもなおリソース不足により十分に対応できないという企業は少なくないでしょう。自社での対応が難しい場合には、そのまま放置するのではなく、プロの知識や技術を利用するアウトソーシングがおすすめです。
アウトソーシングを活用することで、専門性の高い外部サービスの知見を取り入れながら、社内の情報管理体制を強化できます。セキュリティ水準の高い業者に業務を委託することで、機密情報の分散管理が実現し、内部不正による情報漏えいリスクも低下するでしょう。
また、クラウド型システムの導入は、業務効率化の実現に加えて、外敵と内部不正に対する抑止力としても効果的な方法です。扱うデータは、システム提供元による高度なセキュリティ対策の恩恵を受けたクラウドサーバーに保存されるため、端末や事業所にトラブルがあっても影響を受けません。また、アクセス権限管理やログ管理がしやすく、チェック体制の強化ができることから、情報の安全性と透明性を高い水準で維持できます。
このように、セキュリティ対策の骨組みをプロに委託し、無理のない範囲の管理運営を自社でおこなう方法が、安心への近道となるでしょう。
サイバー攻撃では、直接的な金銭的被害よりも、信用の失墜による2次被害のほうが長引く傾向にあります。セキュリティ対策の不備が、長期間の苦難につながることになるのです。
何から始めれば良いのかわからないといったケースでも、ITに関する専門知識とノウハウを備えたプロに相談することで、必要な対策が明確になります。まずは情報収集のつもりで相談してみてはいかがでしょうか。
神奈川 横浜・町田経理アウトソーシングオフィスは、経理・税務・経営に関するお客様のあらゆる課題を解決する総合会計事務所です。創業50年以上の歴史を持ち、約100名の専門家がお客様の事業を力強くサポートします。
約100名体制の経理・税務・経営のプロフェッショナルが、お客様の状況に合わせた最適なソリューションを提供します。複雑な課題も多角的な視点から解決に導き、お客様の成長を強力に後押しします。
会計・経理業務から給与計算、各種コンサルティングまで、DX化推進とアウトソーシングを支援します。これにより、お客様は本業に集中でき、業務の効率化と人件費などのコスト削減を同時に実現します。
最新のクラウド会計システムを積極的に活用し、経営数値のリアルタイムな把握を可能にします。これにより、迅速な経営判断をサポートし、事業の成長を加速させます。
経理・税務の基本サポートに加え、会社設立、相続、さらには医療機関や社会福祉法人に特化した専門的なコンサルティングも提供します。お客様の事業フェーズや業界に合わせたきめ細やかなサポートが可能です。
弊社では、IT知識やセキュリティ対策の経験を積んだ専門家が、貴社のお手伝いをいたします。
丁寧なヒアリングで貴社の状況を分析し、適切なツールの選定や導入のサポート、導入後のフォローも承ります。
バックオフィスの改善や、経理・労務、経営に関するお悩みを信頼できる専門集団に任せたい経営者の方は、ぜひお問い合わせください。



経理体制の
ヒアリング(無料)

貴社の課題解決の
ためのご提案

ご契約
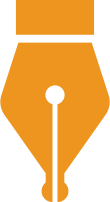
貴社の業務フローの
改善サポートの開始

経理代行業務の
開始