2025.12.28
請求ミスを防ぐ業務フロー整備の実践ポイント
中小企業に多い「1人経理」は、属人化や担当者の業務過多によってミスが多発するリスクがあります。特に、請求処理に関わるミスは、売上の回収遅延や損失だけでなく、取引先の信頼を失うことにもなりかねません。 …
中小企業の経営者にとって、法人税の負担軽減は重要な経営課題の1つです。限られた資源を最大県に活用するために、法令の範囲内で納税額を適正に抑える「節税」は、企業成長と経営の安定性を支える重要な戦略となるでしょう。しかしながら、どのように進めれば良いのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、中小企業が今すぐ実践できる具体的な節税テクニックを10パターン紹介しつつ、節税効果を高める経理業務の効率化についても詳しく解説します。
≪目次≫
法人税とは、株式会社や合同会社などの「法人」が、事業活動によって得た所得に対して課される税金です。企業規模の規模にかかわらず、所得がある法人には原則として納税義務が生じます。
しかし、中小企業の経営者にとって、法人税の負担は決して軽いものではありません。限られたリソースの中で経営を行うには、経営に加え「税金の知識」も必要です。まずは、法人税の仕組みと節税の重要性について、理解しておきましょう。
法人税額は、法人の「課税所得(収益-必要経費)」に税率をかけて算出されます。
中小企業の場合、資本金と収益の規模によって税率が異なる点に注意が必要です。2025年8月時点では、資本金1億円以下の中小法人のうち、年間所得800万円以下の部分には15%、800万円超の部分に23.2%の税率が適用されています。つまり、税率の基準となる利益をいかに適正に抑制するかが、ポイントになるのです。
なかには勘違いしている方もいるようですが、「節税」と「脱税」はまったく違います。節税とは、法令の範囲内で納税額を適正に抑える行為であり、経営上の戦略でもあります。一方、脱税とは意図的に申告内容を偽ったり、所得を隠したりする違法行為で、税法上刑法上の罰則対象となる行為です。
国税庁の統計によると、2023事務年度の法人税の税務調査における申告漏れ件数は4.5万件にものぼり、追徴課税額は1件あたりの平均で約360万円となっています。信頼される企業経営には、節税と脱税の違いを正しく理解し、適切な方法で節税に取り組むことが重要です。
節税によって確保できた資金は、将来の設備投資や人財育成、事業拡大に再投資できます。これによって、将来の事業展開における選択肢を広げる効果もあるでしょう。また、キャッシュフロー改善も可能となり、経営の安定性にもつながります。
中小企業庁の調査では、特に小規模事業者が重要と考える経営課題として「販路開拓・マーケティング」「人手不足」に次いで「資金繰り」が上位に挙げられているのです。限られた経営資源を最大限に活用する工夫が求められている中小企業にとって、適切な節税対策こそ強い味方となるでしょう。
ここからは、実務に生かせる法人税の節約テクニックを10個紹介します。いずれも合法的、かつ効果的な方法ばかりですので、自社の状況に合わせて検討してみてください。
節税の基本でありながら、意外と見落とされがちなのが「経費の計上漏れ」です。領収書の整理が不十分だと、実際に使った経費が適切に計上されず、課税所得を減額するチャンスを逃すことになります。その結果、本来は納める必要のなかった税金まで納付することになりかねません。
計上漏れしやすい経費としては、次のようなものが挙げられます。たとえば、旅費交通費のうち近距離電車の運賃、高速道路代、有料駐車場代などは、領収書が発行されなかったりサイズが小さかったりするため、見落としやすい項目です。また、出先で応急的に購入した消耗品費なども、記録から漏れやすい傾向にあります。
正確な計上を行うためには、領収書等を定期的に整理し、迅速な経費計上を習慣化すると良いでしょう。
法人が従業員に支払う賞与は、一定の条件を満たすことで「損金」としての経費計上が認められます。主な要件は「支給の事前通知・期間内の支払・経理処理」などです。これにより、就業規則などで支給日が定められている規定賞与に加え、臨時支給の賞与も対象となります。
たとえば、当期の利益が思ったより高かった場合など、通知賞与の経費計上による節税効果が期待できます。ただし、通知賞与は通知から1カ月以内に支給を終えなければならないため、資金繰りとの調整も不可欠です。
資金調達(借入)や設備投資(リース)に伴うコストは経費として計上でき、課税所得の圧縮に効果があります。しかしながら、過去に結んだ契約内容が現在の経済環境にそぐわないまま放置され、割高なコストを払い続けているケースが少なくありません。
借り換えや交渉により借入金利を引き下げ、月々の支払利息を減らすことで、長期的なコストダウンが見込めます。また、リース期間の見直しによって、毎月のリース料が抑えられる可能性もあるでしょう。コストの削減と節税を同時に実現させるため、契約内容の定期的な見直しをおすすめします。
単価が10万円未満の消耗品は、一括で経費計上できます。対象は、原則として「購入金額が10万円未満」または「対象年数1年未満」の物品です。具体的には、文房具などの事務用品、事業所の電球や洗剤などの日用品、ガソリンや工具、パソコン周辺機器やソフトウエアなどを含みます。
期末にまとめて購入するなど、タイミングを工夫することで課税所得を抑えられます。ただし、過度な在庫保有を避けるために、実際に業務で使用する範囲内の購入にとどめることも大切です。
建物や機械装置、車両などの減価償却資産の償却方法には、「定額法」と「定率法」があります。このうち、定率法は初年度に多く償却できるため、利益が多い年の節税に効果的です。また、取得金額が30万円未満の減価償却資産については、特例により、一定の要件のもとで即時に全額を損金算入することも可能です。
このように資産の種類や金額、事業の利益状況に応じて、定率法による早期償却か特例による即時償却を選択することで、より柔軟な節税戦略が立てられます。ただし、特例については2026年3月31日までの指定期間があるため注意が必要です。
小規模企業共済は、独立行政法人・中小企業基盤整備機構が整備する小規模企業・個人事業主のための退職金積立制度です。掛金は月々1,000円から70,000円まで任意に設定でき、全額が所得控除の対象となります。
小規模企業共済は、節税と将来の備えを両立できるうえ、納付した掛金総額の範囲内で事業資金貸付も受けられるため、資金調達の選択肢としても役立ちます。
特別償却とは、一定の要件を満たす設備投資に対する税制優遇措置です。たとえば、「中小企業投資促進税制」は、生産性向上や経営力強化を目的とした設備投資に対し、投資初年度に通常の減価償却に加えて特別償却額を計上できます。その際、取得価額の30%の特別償却、または7%の税額控除から選択可能です。
さらに、時代のニーズに応じてデジタル化や脱炭素経営など、時代に応じた設備投資を後押しする制度も登場しています。ただし、指定期間が設けられているものが多いため、活用のチャンスを得るためにも情報に敏感でいることが求められます。
中小企業の場合、年間800万円までの交際費を全額損金として計上可能です。具体的には、取引先との会食費、中元・歳暮などの贈答費、ゴルフ接待費などが該当します。ここで注意すべき点は、1人あたり1万円以下の飲食費は交際費の範囲から除外される点です。この基準は、2024年の税制改正により「1人あたり5000円以下」から「1人あたり1万円以下」に引き上げられました。
しかし、2027年3月31日までの期限付きで、接待飲食費における50%の損金算入が認められています。ただし、領収書とあわせて、飲食等のあった年月日、参加者氏名や関係、人数などの記録を適切に保存しなければなりません。
法人が役員に支払う給与は、一定の要件を満たす場合に限り、損金算入が認められます。原則として、毎月同じ金額であること(定期同額給与)、あらかじめ税務署に届け出た金額であること(事前確定届出給与)、業績指標に基づいていること(業績連動給与)が条件となります。
途中で増減すると損金扱いされないため、年度初めに適正金額を設定しておくことが重要です。また、役員報酬額の決定には、社会保険料の負担も含めた総合的な判断が求められるため、税理士と相談のうえで行うと安心です。
個人事業主の決算は12月と定められていますが、法人は任意に設定できます。この決算日の変更によって、利益を調整しやすくなる場合があります。
たとえば、繁忙期から半年後に決算を設定することで、収益を計画的に費用として計上でき、税負担が安定するでしょう。また、設備投資や大きな支出を予定している時期に決算を合わせれば、減価償却費の形状効果が高まり、利益を圧縮できるのです。
ただし、決算日の変更には税務署への届け出が必須です。取引先や金融機関への影響も考慮し、慎重に検討しましょう。
節税をより確実に、合法的に実行するためには、専門家との連携が不可欠です。顧問税理士や会計事務所との関係を構築しておくことで、より高度な経営判断が可能になります。
適切な節税対策には、税法をはじめとする法律の専門知識が欠かせません。しかし、毎年改正を重ねる法令各種を正しく理解することは至難の業でしょう。無理をせずに、企業会計の知識とノウハウを持つ専門家の指示を仰ぐことが、健全な経営への近道です。
税理士は、税の専門家です。複雑な税制を熟知しており、毎年の税制改正にも精通しています。自社の業種や事業規模、将来の展望を踏まえた最適な節税方法を提案してくれるでしょう。
税務申告にミスがあると、加算税や延滞税といったペナルティを受けるおそれがあります。こうしたリスクを回避するためには、専門家のチェックやサポートを受けることが不可欠です。
試算表や決算書を正確に整え、経営状況を「見える化」してくれる点も大きなメリットです。経営指標を定期的に分析することで戦略を立てやすくなり、経営者の的確な意思決定を支援します。
専門家への相談は、時間制であることが一般的です。限られた時間を有効に使うために、事前に準備しておきましょう。
月次試算表や損益計算書、経費一覧、設備投資計画、借入状況など、最低限の財務情報が必要です。また、「利益をどのくらい圧縮したいのか」「何を課題ととらえ、どのように解決したいのか」など具体的な目標を明確にしておくと、より実務的かつ具体的なアドバイスを受けられます。
税は種類が多いため、税理士ごとに専門分野が異なります。企業会計を専門とし、節税提案や業務効率化の経験が豊富な税理士法人・税理士事務所・会計事務所を選ぶと安心です。
初回無料相談サービスなどを活用して、提案内容の具体性、費用対効果の明確さ、話しやすく説明が分かりやすいかなどをチェックしておくと良いでしょう。
クラウド型会計システムとは、インターネットを通じてクラウドサーバー上にあるシステムを操作する方法です。こうしたシステムの導入には以下の効果が期待でき、経理業務の効率化と節税を両立させる手段として注目されています。
クラウド型会計システムを導入する最大のメリットは、定型業務の自動化です。金融機関との連携や店舗のPOSレジとの連動により、収支データの取得から仕訳記帳、集計までを自動で行います。
なかでも、領収書をスマホで撮影するだけで紙面の情報をデジタル化する機能は、経費計上の漏れやミス防止に効果的です。さらに、経理以外の従業員でも領収書の登録が容易になるため、実際の支払いと計上月のずれを防ぎます。正確かつ計画的な経費計上に貢献するでしょう。
記帳作業の自動化でヒューマンエラーが消滅し、経理データの正確性が向上します。また、あらかじめ設定した仕訳ルール、最新の税法に従って集計されるため、税務申告に必要な資料が正確かつ迅速に整います。
領収書・請求書データは、電子帳簿保存法に対応した方法で電子保存されるため、書類管理の効率化と申告ミスリスクの低減も可能です。
日々の取引データは自動で記録され、リアルタイムで反映されます。常に、最新の財務状況が確認できるというわけです。これにより、月次や四半期ごとの利益予測、年間の納税額試算などが容易になり、効果的な節税対策の検討材料として役立ちます。
たとえば、第3四半期時点で予想以上の利益が出ているから、設備投資の前倒しや決算賞与を検討するなど、具体的な対策を早期に講じることができるのです。
クラウド上でデータを共有することで、税理士とのやり取りもスムーズになります。帳簿や資料の現物を発送する手間やコストを削減できるうえ、紛失リスクもありません。オンライン会議ツールで画面共有をしながら監査を実施することも可能です。
また、リアルタイムデータを確認しながら、具体的な節税対策を講じることができ、より実効性の高いアドバイスが得られるでしょう。
中小企業にとって、法人税の節税は「お金を守る」ことにとどまらず、「経営の柔軟性を高める」ことにもつながります。
今回紹介した10のテクニックは、いずれも法令にのっとった実践的な方法です。そして、その効果を最大限に引き出すためには、クラウド型会計システムの導入による業務効率化や信頼できる税理士との連携が欠かせません。
弊社では、丁寧なヒアリングによって貴社の課題を見つけ出し、最適化を図るためのアドバイスを行うことが可能です。
クラウド型会計システムの選定から導入支援、導入後のサポートまで一貫してお引き受けいたします。
節税を経営の武器に変えるために、まずは貴社の現状を見つめ直し、できることから一歩ずつ取り組んで見てはいかがでしょうか。
無料相談サービスやオンライン面談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
神奈川 横浜・町田経理アウトソーシングオフィスは、経理・税務・経営に関するお客様のあらゆる課題を解決する総合会計事務所です。創業50年以上の歴史を持ち、約100名の専門家がお客様の事業を力強くサポートします。
約100名体制の経理・税務・経営のプロフェッショナルが、お客様の状況に合わせた最適なソリューションを提供します。複雑な課題も多角的な視点から解決に導き、お客様の成長を強力に後押しします。
会計・経理業務から給与計算、各種コンサルティングまで、DX化推進とアウトソーシングを支援します。これにより、お客様は本業に集中でき、業務の効率化と人件費などのコスト削減を同時に実現します。
最新のクラウド会計システムを積極的に活用し、経営数値のリアルタイムな把握を可能にします。これにより、迅速な経営判断をサポートし、事業の成長を加速させます。
経理・税務の基本サポートに加え、会社設立、相続、さらには医療機関や社会福祉法人に特化した専門的なコンサルティングも提供します。お客様の事業フェーズや業界に合わせたきめ細やかなサポートが可能です。
バックオフィスの改善や、経理・労務、経営に関するお悩みを信頼できる専門集団に任せたい経営者の方は、ぜひお問い合わせください。



経理体制の
ヒアリング(無料)

貴社の課題解決の
ためのご提案

ご契約
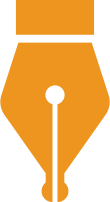
貴社の業務フローの
改善サポートの開始

経理代行業務の
開始