2025.12.28
請求ミスを防ぐ業務フロー整備の実践ポイント
中小企業に多い「1人経理」は、属人化や担当者の業務過多によってミスが多発するリスクがあります。特に、請求処理に関わるミスは、売上の回収遅延や損失だけでなく、取引先の信頼を失うことにもなりかねません。 …
経済産業省は「2025年の崖」を提示し、レガシーシステムの老朽化と属人化による業務停止リスクに警鐘を鳴らしています。こうしたリスクが、中小企業の抱える「1人経理の高齢化リスク」と重なる点も見逃せません。突然の退職や休職で経理担当者がいなくなれば、ブラックボックス化した経理業務は停滞し、企業の継続性まで揺らぎかねないのです。
本コラムでは、「2025年の崖」を乗り越えるために、経理DX(デジタルトランスフォーメーション)の第一歩として有効な5つの実践的対策を紹介します。
≪目次≫
中小企業における人材の高齢化は、もはや避けることのできない深刻な問題です。まずは客観的な資料から状況を把握しておきましょう。
1970年代後半から続く出生率減少による「少子化」、社会保障の充実や医療技術の発展で平均寿命が延びたことによる「高齢化」は、日本社会における深刻な課題です。内閣府の発表によると、総人口のうち65歳以上が約30%を占め、生産年齢である15~64歳は約60%となっています。
こうした少子高齢化に対応すべく制定されたのが「高齢者雇用安定法」です。すべての企業は65歳までの雇用確保が義務づけられ、70歳までの就業確保も努力目標とされています。実際に65~74歳の約45%が何らかの形で就労しており、労働力人口に占める65歳以上の比率は上昇傾向にあるのです。
特に中小企業では、シニア世代の雇用に積極的だといえるでしょう。総務省「就業構造基本調査」によると、雇用者数に占める60歳代および70歳以上の割合は、企業規模が小さいほど高くなる傾向にあります。具体的には、従業員300人以上の企業では約10%にとどまる一方で、20~299人規模では約19%、5~19人規模では約25%、そして4人以下の企業では約38%に達しています。
高齢化が進むほど、急な退職や休職を余儀なくされる可能性は高まります。
例えば、悪性腫瘍や肝硬変などの重篤な疾患は、一般的に50代以上で発症しやすいとされています。また、生活習慣からくる血圧・中性脂肪・血糖値にかかる数値の悪化は、脳梗塞や急性心筋梗塞を引き起こしかねません。さらに、65歳以上では認知症の発症リスクも上昇します。
あるいは、本人が元気に働いていても、親の介護が急に始まり仕事を続けられなくなるケースもあるでしょう。このような「療養・介護が必要な状況」は、前兆を伴ってやってくるとは限りません。退職日を決め、新規採用を行い、引継ぎを済ませてから円満に退社できるケースばかりではないのです。
中小企業では若手の採用が困難で、ベテラン社員に頼らざるを得ない状況が続いています。なかでも経理業務は、会計業務や給与計算などお金に関する業務を「1人経理」が一手に引きうけ、長年担当しているケースが一般的です。
では、その1人経理担当者が、もしも明日から出社できない状況になってしまったら、どうなるのでしょうか。
リソースに限りのある中小企業では、1人あたりの担う業務範囲が多いため、担当者外の業務知識はないことがほとんどです。そのため、1人経理が不在になれば、たちまち日々の経理業務は停滞するでしょう。
経理業務の停滞によって起こる具体的な問題は、以下の通りです。
経理業務は、会社のお金の流れを記録管理する重要な役割を担っています。この記帳が滞ると、現在の業績や資産残高などが把握できず、適切な経営判断をくだせません。また、買掛金の支払遅延を起こしてしまうと、取引先との信頼関係を損ない、今後の取引に応じてもらえなくなる可能性もあるでしょう。さらに、売掛金の回収ができなければ、資金繰りにも影響が出ます。
期日までに正しい額の給与を支払えなかったり、従業員が立て替えた経費の精算ができなかったりすると、社内の信用も失います。給与やお金に関する不安や不満は離職に直結するものです。そのため、人材流出を起こしてさらなる人材不足を招くおそれもあります。
1人経理は業務手順を共有する必要がないため、マニュアル化されていないことがほとんどです。たとえ、経理担当者の後継人材を補充できても、まずはブラックボックス化している業務フローを手探りで再構築する必要があり、正常化までには時間がかかります。
業務プロセスを特定の担当者に依存している状況を、属人化といいます。1人経理期間が長いほど、独自の手順による処理が増え、属人化が進むのです。この属人化を、1人経理が健在なうちに解消しておくことが、高齢化対策の鍵となります。
ここからは、具体的かつ実践的な対策を5つに分けて紹介しましょう。
経理部門には、請求・売掛金管理、支払・買掛金管理、仕訳記帳・集計、経費精算管理、決算報告書作成、税務申告書作成、勤怠管理・給与計算などさまざまな業務があります。
まず業務フローを確認し、重複や遠回りなどのムダを洗い出しましょう。このとき、経理業務だけでなく、お金が関わるすべての流れに目を向けることが重要です。例えば、営業会議で使う資料作成で経理データの出力を待つケースなど、経理業務がボトルネックとなっている状況も明らかにします。
業務フローの最適化に合わせて、経理業務のマニュアルを作成しておきましょう。マニュアルが整備されていれば、経理担当者の不在に慌てる必要はありません。急な退職・休職に限らず、一時的な不在にも代行を立てやすくなります。業務停滞に配慮して休暇が取りにくい状況も、マニュアル整備によって改善されるでしょう。
1人経理の業務効率化には、クラウド型の会計システムがおすすめです。
システムやデータがクラウドサーバーにあるクラウドツールなら、アクセス権を持つ従業員は時と場所を選ばずにデータを閲覧できます。例えば、会議資料作成はもちろん、営業部門で買掛金の支払状況を把握したり、取引先で財務データを確認したりすることが可能です。これらは、1人経理に依存した属人化とボトルネックの解消、さらにはスピーディな経営判断にもつながります。
また、オンライン連携による自動化もクラウド型会計システムの大きなメリットです。あらかじめルールを設定しておくことで、銀行口座、法人カードや交通系ICカード、販売店のPOSレジなどの取引データの取得から仕訳記帳、集計までが自動化されます。さらに、勤怠管理データからの給与計算も自動化可能です。これにより、転記漏れや計算ミスといったヒューマンエラーが減少し、経理データの精度向上が実現します。
従業員のライフスタイルや健康状態に応じて、働く時間や場所を選べる仕組みがあれば、高齢者や介護・育児などの事情を抱える人材も、無理なく働き続けることができるでしょう。特に、中小企業では、限られたリソースの中で人材を確保・定着させるために、働きやすい環境づくりが不可欠です。
時短勤務やフレックス制など、勤務時間に柔軟性を持たせることで健康や家庭の事情に対応しやすくなります。また、クラウド型会計システムやオンライン会議ツール、ビジネスチャットなどのクラウドツール導入により、在宅でも業務を円滑に進められます。こうした環境整備が、高齢者の継続雇用を支援し、ゆとりを持って後任育成や引き継ぎができる体制づくりにつながるのです。
働きやすい環境になり職場への満足度が高まれば、中堅社員や若手社員の離職率は自然と下がります。また、離職率の低い企業は求職者にとっても魅力的な存在です。さらに、評価方法や福利厚生・研修体制の充実が、モチベーションの向上につながります。
クラウド型会計システムの導入により、定型業務の多くを自動化することで、作業工数を大幅に削減できます。その結果、1人経理はシステム操作やイレギュラー対応、決算業務など、専門性を生かした業務に集中できるようになります。さらに、給与計算や他のバックオフィス業務へリソースを再配分することも可能です。
加えて、マニュアル整備などを通じて、遅延が許されない経理業務の代行がしやすい環境整備も重要です。他部門の社員にも基本的な経理知識を習得させることで、繁忙期の業務分散が可能となり、結果として社内全体の業務効率が向上します。
業務フロー改善やシステム導入についての研修は、経理部門だけでなく社内全体で共有しましょう。経理システムへの理解が社内に浸透することで、部門間の連携がスムーズになります。また、経費精算や休暇申請などの手続きを申請者自身が行うことで、バックオフィス業務の自律化が進み組織全体の生産性向上にもつながります。クロストレーニングの取り組みは、業務の属人化を防ぎ、チーム全体の柔軟性や対応力を高めるために有効です。
クラウドツールの導入や職場環境の改善によって、労働力不足の解消が期待できます。しかしながら、業務フロー改善やシステム導入にかかる時間を待てない、あるいは改善作業に割くリソースがないという企業も少なくありません。
そうしたケースでは、外部の経理専門会社に一部または全部の業務を委託する方法が有効です。サービス内容や料金体系を事前に比較検討し、自社にとって最適な方法を見つけましょう。
アウトソーシングは、会計業務の専門家に経理業務を委託する方法です。専門知識やスキルを持つプロに処理を委託できるため、業務の正確性向上が期待できます。クラウド型会計システム導入との併用により、経理データのリアルタイム共有も可能です。一方で、経理業務のノウハウが自社に残りにくく、柔軟性やコスト面に注意が必要です。
アウトソーシングは、業務プロセスごとの一任から部分的な委託まで、幅広い選択が可能です。経理担当者が在籍しているうちに、さまざまなプランを検討しておくと良いでしょう。記帳代行、給与計算、請求管理など、自社の状況に合わせて段階的に委託していく方法もあります。
1人経理のアウトソーシングについては、下記記事でも詳しく解説しています。
【徹底比較】1人経理の解消には、アウトソーシングか?人材派遣か?
2025年は団塊の世代(第一次ベビーブーム世代・1947~1949年生まれ)の全員が75歳以上となる年です。多くの企業で人材の引退が予想され、労働力不足が悪化する可能性があります。
経理業務は会社経営の基盤を支える重要なインフラです。だからこそ、備えは早ければ早いほど、安心だといえるでしょう。
本コラムでも解説したように、突然の不在に備えることは職場環境の柔軟性を高めることにもつながります。
経理アウトソーシングオフィスでは、こうした問題に対処するためのさまざまなサービスを提供しています。
システム導入についても、経理フローの最適化からクラウドツールの選定、導入サポート、運用開始後のフォローアップまで、一貫してご提供可能です。
バックオフィスのDX化が推進されている今、IT導入補助金などの国の後押しが使える可能性もあります。
オンライン相談や無料相談も承っておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
神奈川 横浜・町田経理アウトソーシングオフィスは、経理・税務・経営に関するお客様のあらゆる課題を解決する総合会計事務所です。創業50年以上の歴史を持ち、約100名の専門家がお客様の事業を力強くサポートします。
約100名体制の経理・税務・経営のプロフェッショナルが、お客様の状況に合わせた最適なソリューションを提供します。複雑な課題も多角的な視点から解決に導き、お客様の成長を強力に後押しします。
会計・経理業務から給与計算、各種コンサルティングまで、DX化推進とアウトソーシングを支援します。これにより、お客様は本業に集中でき、業務の効率化と人件費などのコスト削減を同時に実現します。
最新のクラウド会計システムを積極的に活用し、経営数値のリアルタイムな把握を可能にします。これにより、迅速な経営判断をサポートし、事業の成長を加速させます。
経理・税務の基本サポートに加え、会社設立、相続、さらには医療機関や社会福祉法人に特化した専門的なコンサルティングも提供します。お客様の事業フェーズや業界に合わせたきめ細やかなサポートが可能です。
バックオフィスの改善や、経理・労務、経営に関するお悩みを信頼できる専門集団に任せたい経営者の方は、ぜひお問い合わせください。



経理体制の
ヒアリング(無料)

貴社の課題解決の
ためのご提案

ご契約
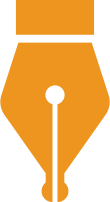
貴社の業務フローの
改善サポートの開始

経理代行業務の
開始