2025.12.28
請求ミスを防ぐ業務フロー整備の実践ポイント
中小企業に多い「1人経理」は、属人化や担当者の業務過多によってミスが多発するリスクがあります。特に、請求処理に関わるミスは、売上の回収遅延や損失だけでなく、取引先の信頼を失うことにもなりかねません。 …
コロナ禍を経て、再びオフィスや現場に人が戻りつつあります。「テレワークは非常時の対策で、平時の運用は難しい」と決めつけてはいないでしょうか。
実際には、経理や勤怠管理、給与計算といったバックオフィス業務は、クラウドツールを活用することで平時から十分にテレワーク対応が可能です。特に中小企業では、限られたリソースで多くの業務をこなす必要があり、業務負担の偏りや属人化といった課題を抱えています。テレワークは、こうした課題の解決にもつながる有効な手段です。
本記事では、中小企業のバックオフィス業務の中でも、特にテレワークに適した業務を整理し、そのメリットや導入に向けた準備のポイントをわかりやすく解説します。
<目次>
「現場業務があるから、テレワークはできないだろう」「緊急事態は脱したのだから、テレワークなんていらないのでは?」と考える方も少なくないでしょう。
新型コロナウイルス感染拡大防止策として、テレワークの利便性は実証されました。感染状況が落ち着いた現在では、多くの中小企業で出社回帰の動きが見られます。その背景には、対面でのコミュニケーションや勤怠管理の不安、紙文化やハンコ決裁といった従来の業務スタイルへのこだわりがあると考えられます。
しかし、テレワークは、中小企業にとって多くのメリットをもたらします。緊急事態だけの対策だと考えると、その効果を逃すことになるでしょう。
出社の機会が減る分、通勤交通費の支給額を削減できます。また、オフィスの光熱費や維持費、スペースの縮小に伴う賃料削減など、各方面でコストダウンが可能です。
また、勤務地にしばられない働き方は、優秀な人材の獲得と定着に直結します。多様な人材を採用しやすくなるため、企業競争力も向上するでしょう。育児や介護などの事情を抱える従業員も働き続けやすくなり、離職率の低下にもつながります。
従業員にとって、通勤ストレスが軽減し、業務を自律的に進められることでモチベーションがあがり、生産性の向上が期待できるでしょう。
さらに、感染症対策として有効なことは実証済みであり、本人や家族に何らかの感染症状が出た場合にもテレワークを実施することで、拡大を防ぐことができます。大きな災害が起こったときも、テレワークならは、帰宅困難リスクがありません。
テレワーク導入のメリットについては、下記コラムでも詳しく説明しています。
https://keiri-outsourcing.com/?post_type=column&p=10681&preview=true
250704_中小企業こそ効果大!テレワーク導入で実現する業務効率と人材確保
テレワークに適した業務には、いくつかの共通点があります。各業務の性質を正しく把握することで、どの自社業務がテレワークに向いているのか、段階的に進める場合はどのように優先順位をつけるのかを見極めることができるでしょう。
社内に限定されず、1人で進められる業務はテレワーク向きです。具体的には、データ入力や分析、レポート作成、計画策定などが該当し、これらの業務は集中して取り組むことで高い成果を上げやすい特徴もあります。
成果を可視化しやすい業務や定量的に測定できる業務は、テレワークとの相性が良いでしょう。働いている姿を見なくとも、成果物によって仕事をしたことが明確になるからです。進捗状況も明確なため管理者やチームが把握しやすく、適切な評価につながります。
テレワークでは、社外でも情報漏えいリスクを管理できることが重要です。現在では、多くのクラウドサービスが高度なセキュリティ機能を備えているため、VPN(仮想プライベートネットワーク)の併用でデータアクセスを制限できれば、テレワークの障壁は大きく低減します。
ただし、人が多いカフェなどで作業する際は、背後からの視線にも注意しなければなりません。扱う情報の機密レベルに応じて作業環境を考慮するなど、従業員の意識を変える研修も必要でしょう。こうしたセキュリティ対策を実施することで、機密性の高い業務でもテレワーク対応が可能になります。
また、中小企業では会計処理に加え、勤怠管理や給与計算、税務対応など「お金にかかわる業務」をごく少人数の担当者が扱う「1人経理」が一般的です。1人経理は属人化しやすく、担当者がいなければ業務が回らない状況に陥ります。このことからも、「1人経理は、社内にいる必要がある」と思い込んではいないでしょうか。
しかし、クラウド化の普及により、経理業務の多くがテレワーク対応可能になっています。
ここでは、経理業務にテレワークを導入して効率化するためのポイントを解説します。
クラウド型会計システムとは、作業やデータ保存をインターネット上のクラウド環境で行う会計管理ソフトウエアのことです。従来のインストール型とは異なり、場所や端末を問わずアクセスできるため、テレワークの導入には欠かせません。
また、作業に必要な資料も成果もクラウド上に保存するため、複数人数での情報共有を容易にします。テレワークに備えて資料を持ち帰ったり送付したり、成果物を持って出社したりする必要はありません。成果はリアルタイムでクラウドツールに反映されるため、経営者は経営戦略を立てやすくなるでしょう。
さらに、社外秘データを物理的に持ち運ばずに済むため、セキュリティ面でのリスクも減らせます。万が一、社内のパソコンが故障しても、クラウド上のデータには影響がありません。
クラウド型会計システムを導入する最大のメリットは、作業の自動化です。金融機関が扱う企業間売買などの取引データ、POSレジに記録されている店舗の売り上げなどを自動取得し、あらかじめ設定したルールに基づいた仕訳記帳を行います。
これにより、記帳漏れや転記ミスといったヒューマンエラーが消滅し、経理データの精度が向上します。加えて、サービス提供元のアップデート・メンテナンスがあるため、常に最新の法律・制度を遵守した適切な処理が可能です。
クラウド化によってテレワークが可能となる業務には、以下が挙げられます。
クラウド型会計システムの導入で、仕訳記帳のうち定型業務は自動化されます。オペレーターの作業は、イレギュラーな仕訳記帳対応と自動化による成果のチェックが主となるため、テレワークでも十分に対応できます。
クラウドツールは、請求・支払にかかる処理についても自動化します。オペレーターは確認作業や必要に応じた調整をすれば良く、その結果は経営陣や営業部とクラウド上で共有可能です。
財務情報はクラウドツールで一元管理されており、任意の条件による集計・レポート出力を自動で行えます。この出力データは、アクセス権限を持つ従業員なら誰もが閲覧可能なため、よほどのイレギュラーでもなければ、社内対応をする必要はないでしょう。
一方、クラウド型会計システムを導入するだけではテレワーク対応が難しい業務もあります。すべてをデジタル化することはできますが、多くの資金と人員を投入しなければならず、リソースに限りのある中小企業では現実的ではありません。
しかしながら、月に1日も出社しない完全テレワークを導入する企業は珍しく、週に数日出社とテレワークを混在させるハイブリッド型が一般的な方法です。「すべてをデジタル化しなければ、テレワーク導入できない」と考えるのではなく、「テレワークに向かない業務は出社時に」と柔軟に考えれば良いのです。
電子帳簿保存法の施行によって、電子取引を行った請求書・領収書についてはデジタル化が進んでいます。しかし、過去の帳票までは手が回らず、依然として紙資料が残っているところも多いでしょう。こういった資料を参照する作業や、資料そのもののデジタル化作業などは、出社が必須となります。
ハンコ文化が残っている企業では、決裁のための出社対応が必要です。デジタル承認システムを導入する方法もありますが、定着に時間がかかるケースも考えられます。急ぎの場合は、前もってPDFなどを共有して仮承認するフローを整備しておくと安心です。
現金の取り扱いは、物理的な管理と対応が求められます。現金の扱いを最小限に抑えるためには、法人クレジットカードや交通系ICカードなどを含むキャッシュレス決済の導入が効果的です。さらに、精算請求や関連処理を自動化でき、効率アップにもつながります。
法定保存義務がある紙書類は、社内管理が基本となります。電子化が可能なものについては、段階的にデジタル保存への移行を進めておくと良いでしょう。
クラウド型会計システムは、当期の財務データから適切な税務資料まで自動作成可能です。しかし、紙資料との照合や監査の立ち会いなどで、出社が必要になるケースは多くあります。事前準備やデータ整理はテレワークで集中的に進めておくと効率的です。
1人経理が担うことが多い勤怠管理や給与計算も、条件がそろえばテレワークでの対応が可能です。企業規模が小さい場合、給与額や休暇・社会保険状況などを扱う際に、他の社員との距離感が気になるという声をよく聞きます。テレワークで行えば、社内の目を気にせずに一気に片づけられるため、効率アップにもつながるでしょう。
勤怠管理・給与計算に対応したクラウドシステムを導入することが、テレワーク化への第一歩です。このとき、クラウド型会計システムとの連携や、既存の勤怠管理・給与計算ソフトとの互換性が重要なポイントになります。
また、スマートフォンやパソコンから出退勤を打刻して集計する機能も、テレワークには不可欠です。これにより、自宅や社外で働く時間をリアルタイムで正確に記録して一元管理することが可能になります。
クラウドツールによる一元管理、情報共有のしやすさにおり、以下の勤怠管理・給与計算業務もテレワークで扱えます。
デジタルタイムカード機能により、従業員の出退勤データは勤怠管理システムが自動集計します。出社やテレワーク、時短勤務など、多様な働き方に対して柔軟に対応可能です。
集計自体は自動化されるため、オペレーターは確認作業を行います。当月の勤務時間をリアルタイムで把握できるため、働き方改革に伴う時間外労働の時間制限など、労働基準法に基づく適切な管理が実現します。
オンラインシステムにより、紙書類を介さず直接的な申請と承認が可能です。承認フローが可視化され、処理状況の把握も容易で管理しやすくなります。
勤怠データを連携し、給与計算が自動化されます。計算ミスや転記漏れといったヒューマンエラーがなくなり、給与管理の正確性が向上します。ミスが許されないプレッシャーから解放され、1人経理担当者のストレスも軽くなるでしょう。
自動化により、最新の税制に合わせた計算から適用のタイミングまで適切に行われます。従業員個々で異なる税金対応も自動化することで、担当者の負担軽減と精度向上が両立するでしょう。
電子化により紙での発行が不要になり、担当者は封入作業から解放されます。デジタル化以降の過去データも含め、給与明細はWEB上でいつでも確認できるようになり、従業員の利便性も向上します。
クラウドシステムの導入で、勤怠管理・給与計算にかかる業務はほとんどが自動化されるでしょう。1人経理担当者は、これまでの知識やノウハウを生かして適切なチェックを行うことが主な業務となります。
一方で、以下のような業務はアナログの壁が厚く、出社による対応が必要です。段階的に改善され、将来的にはこれらの業務もデジタル化、あるいはなくなっていくでしょう。
紙のタイムカードに打刻する方法を継続する場合は、月末ごとにタイムカードの転記や集計作業を行うための出社対応が必要となります。従業員数分の作業が必要で負担が大きいため、迅速なデジタル化が望まれます。
集計や給与反映までは自動化されていても、紙の明細が必要だと考える企業は少なくありません。その場合は、出社対応による印刷・封入・配布作業が不可欠です。
インターネットバンキング未導入の場合は、銀行窓口に出向く必要があります。一般的に銀行業務の集中する時期と重なるため、大きく時間を割かなければなりません。これらは、オンラインバンキングの導入により、解決します。
紙の納付書ベースでの処理が必要なケースでは、出社対応が発生します。しかしながら、電子納税への移行により改善可能です。
上長の承認や紙ベースの書類が必要な場合は、出社が必要になります。アナログフローの見直しが改善の鍵となるでしょう。
バックオフィス業務のテレワークを成功させるためには、単にシステムを導入するだけでなく、組織全体で取り組むことが重要です。クラウド化による業務改革は、従来の働き方や業務プロセスを根本的に見直し、業務効率化を目指す好機となります。
ここでは、テレワーク推進とクラウド化を進める際の重要なポイントを解説します。
1人経理における属人化は、ミスや不正のリスクがある危険な状態です。クラウドツールを導入すると、経理業務フローを最適化し標準化することができ、特定の担当者に依存する属人化の解消につながります。
リアルタイムでの情報共有が可能になると、各部門が閲覧したいデータを自由に引き出せるようになります。担当者不在時の業務停滞や情報更新のタイムラグがなくなり、企業全体の業務効率が向上するでしょう。
多くの業務が自動化することで、ヒューマンエラーが減少します。また、ログの取得や遠隔監視、データのリアルタイム閲覧などにより、不正やミスの早期発見に役立ちます。これらのことから、経理データの精度があがり、信頼性も大幅に向上するでしょう。
クラウドツールの導入で、電子帳簿保存法やインボイス制度、年末調整のWeb対応など、最新の法令にも適切な対応が行えます。また、新たな税制改正や会計基準の変更があっても、提供元のアップデートにより自動で対応するため、常に最新の法的要件を満たした処理が可能です。
これにより、経理担当者が独自で情報を集め、難解な税法を理解する努力を行う必要はありません。
クラウドシステム選びは、自社の規模・業態・課題に合ったものを選ぶことが重要です。既存システムとの連携や、契約している税理士との連携がとれるかどうかも、忘れずに確認しましょう。
導入前には必ず無料トライアルを活用し、実際の業務フローでの使い勝手を検証することをおすすめします。また、将来的な事業拡大や業務変更を予定している場合は、システムの拡張性も重要な選択基準の1つです。コストだけでなく、長期的な運用を見据えた総合的な判断が求められます。
自社に合うシステムがわからない、リソース不足で手が回らないという場合には、専門的な導入サポートの活用を検討してみてはいかがでしょうか。
特に、業務フローの見直しから運用開始まで一貫したサポートを受けられるサービスを選ぶことで、導入成功率を高めることができます。また、従業員への教育研修や運用後のフォローアップも含めた包括的なサポートを受けることで、組織全体でのスムーズな移行が実現するでしょう。
経理や勤怠・給与管理などのバックオフィス業務は、クラウド化を進めることでテレワークにも十分対応可能です。現場業務があるからといって、すべての業務が出社必須というわけではありません。業務の特性や社内環境に合わせて、柔軟に出社とテレワークを組み合わせることができます。
クラウドツールの導入は、業務の効率化・標準化を促進し、属人化の解消やミスの減少、法令遵守の強化にもつながります。
弊社では、貴社の環境に応じて、業務フローの見直しから、テレワークに対応できるシステムの選定・設計、アフターサポートまでを真摯に支援させていただいております。
もちろんご相談内容は守秘義務により厳重に守られますので、ご安心ください。
完全無料!オンライン面談OK!まずはお気軽にご連絡ください!
神奈川 横浜・町田経理アウトソーシングオフィスは、経理・税務・経営に関するお客様のあらゆる課題を解決する総合会計事務所です。創業50年以上の歴史を持ち、約100名の専門家がお客様の事業を力強くサポートします。
約100名体制の経理・税務・経営のプロフェッショナルが、お客様の状況に合わせた最適なソリューションを提供します。複雑な課題も多角的な視点から解決に導き、お客様の成長を強力に後押しします。
会計・経理業務から給与計算、各種コンサルティングまで、DX化推進とアウトソーシングを支援します。これにより、お客様は本業に集中でき、業務の効率化と人件費などのコスト削減を同時に実現します。
最新のクラウド会計システムを積極的に活用し、経営数値のリアルタイムな把握を可能にします。これにより、迅速な経営判断をサポートし、事業の成長を加速させます。
経理・税務の基本サポートに加え、会社設立、相続、さらには医療機関や社会福祉法人に特化した専門的なコンサルティングも提供します。お客様の事業フェーズや業界に合わせたきめ細やかなサポートが可能です。
バックオフィスの改善や、経理・労務、経営に関するお悩みを信頼できる専門集団に任せたい経営者の方は、ぜひお問い合わせください。



経理体制の
ヒアリング(無料)

貴社の課題解決の
ためのご提案

ご契約
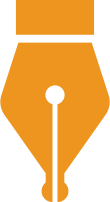
貴社の業務フローの
改善サポートの開始

経理代行業務の
開始