2026.01.30
副業時代に経営者が知っておくべき税務知識と「副業300万円問題」の最新動向
2017(平成29)年の「働き方改革実行計画」で副業・兼業の促進が明確に示されて以来、柔軟な働き方がしやすい環境整備の一環として、副業を認める会社は増加しています。そのため、経営者にとっても、副業…
近年、多くの企業でDXが進展していますが、その多くは営業や製造といった現場部門に集中しがちです。しかし、実はバックオフィス業務、とりわけ経理業務こそ、DXによる効率化の恩恵を大きく受けることができます。本記事では、経理効率化の次なる一手として、アウトソーシングとクラウド連携によるスマートな業務改善手法について解説します。
目次
1.クラウド会計を導入しても残る「手作業」の壁
1-1.デジタルとアナログが混在しやすい業務例
1-2.アナログ作業が残る要因とは?
1-3.人を増やす余裕がない
2.経理のプロセスを「まるごと任せる」という選択肢
2-1.「経理アウトソーシング+クラウド連携」による7つのメリット
2-2.無料相談を効果的に利用
3.まとめ
クラウド会計ツールを導入する企業は年々増加しています。しかし、導入後も業務全体の効率化には至らず、手作業が多く残っているケースが少なくありません。
特に中小企業では、1人で経理業務を担うことが多く、業務負担の軽減には限界があります。クラウドツールを導入しても、伝票整理や確認作業などのアナログ業務が残り、十分な効率化が難しい課題が浮き彫りになっています。
経理業務のデジタル化が進んでいる一方で、アナログ作業が根強く残るケースは少なくありません。部分的にツールを導入しても、取引先や業務フロー全体がデジタル対応していなければ、手作業が発生しやすくなります。以下に、特にデジタルとアナログが混在しやすい具体例を挙げて解説します。
電子帳簿保存法に対応したデジタル管理ツールを導入しても、取引先からは依然として紙やPDFファイルによる請求書が届くことも多いでしょう。そうなると、自社でも手作業による登録や保存が必要です。こうした状況では、完全なペーパーレス化が実現できず、業務効率化を妨げる要因となります。
入金データ管理では、銀行口座からのデータ取り込みを自動化するだけでは不十分な場合があります。入金情報の手動入力、取引先との照合作業、仕訳の手動作成、さらに入金ミスマッチ時の修正対応など、多くの人的作業が必要です。これにより、作業負担が増加しヒューマンエラーリスクも高まります。
給与計算業務は、勤怠管理だけでは完結しません。従業員の給与から控除する所得税や住民税、社会保険料の計算など、複雑な手続きにはアナログ対応が残りがちです。正確な控除額を算出し、期日までに納付するためには、手作業による確認が欠かせない場面も多くあります。
経理業務をデジタル化しようとしても、アナログ作業が完全に解消されないケースは少なくありません。ここでは、アナログ作業が残る代表的な要因を整理し、効率化に向けた課題に触れていきます。
部分的なクラウドツール導入によるデジタル化では、対象業務以外に手作業が残ります。一部でもデジタル化することで利便性が向上するケースもあれば、二度手間が発生してかえって効率が低下するケースもあるでしょう。全体最適を考慮した導入戦略が重要です。
クラウドツールを導入しても、既存の会計システムや業務ソフトと連携できなければ、データ移行や照合作業を手動で行う必要があります。このような連携不足は、入力ミスや確認作業の増加を招き、業務効率化の妨げになります。導入時には、既存環境との互換性チェックが不可欠です。
導入するクラウドツールが、自社の業務要件に適していることも重要です。カバーできない業務がある場合は、手作業や別のツールで補完する必要が生じます。結果として、業務フローが分断され、効率化効果が薄れるでしょう。導入前には、自社の業務プロセスとツールの適合性を丁寧に確認することが求められます。
担当者がクラウドツールを十分に活用できなければ、アナログ作業に頼らざるを得ません。特に、設定やカスタマイズに対応できるITスキルが不足していると、ツールの性能を生かせず、導入効果が限定的になります。教育・サポート体制の整備が鍵となります。
クラウドツールを導入しても、それだけで業務効率化が実現するとは限りません。既存の業務フローを見直さなければ、無駄な作業が残り、効果が半減します。導入時には、現状の業務プロセスの棚卸しと最適化を図ることが、業務改善につながります。
セキュリティリスクへの懸念から、ツールの活用範囲を制限し、あえてアナログ作業を残すという企業もあるでしょう。たとえば、重要な情報を手作業で管理するケースなどが挙げられます。リスク管理は重要ですが、過度な制限は非効率を招きます。適切なセキュリティ対策とデジタルツールの活用をバランス良く組み合わせることが求められます。
「デジタルとアナログの混在」によって、クラウド化による業務効率化のメリットを得にくくなっているケースも見られます。特に月末・月初の決算業務や税務申告期には残業が常態化し、働き方改革の流れにも逆行します。本来であれば、人員を増やして対応すべきですが、中小企業では人件費や採用コストの負担が大きく、簡単には踏み切れないのが実情です。
東京商工会議所の調査でも、約8割の中小企業がITを「導入」している一方で、「活用」している企業は約5割にとどまっていることを示唆しています。
参照元:東京商工会議所「中小企業のデジタルシフト・DX実態調査 集計結果」2025年1月10日 中小企業のデジタルシフト・DX推進委員会
業務効率化の次のステップとして注目されているのが、「経理プロセスのアウトソーシング(BPO)」という選択肢です。これは単なる部分的な経理代行とは異なり、記帳、支払業務、債権債務管理など、経理業務全体を一括して外部に委託する仕組みです。
これにより、部分的クラウド化やシステム連携不足、手作業の残存といった課題を根本から解消できます。さらに、限られた人員でも安定した経理運営が可能となり、経営資源を本業に集中させる体制を構築できます。
近年では、経理プロセスのアウトソーシングと同時に、クラウド会計システムを自社に導入する企業が増えています。この「経理アウトソーシング+クラウド連携」により、単なる作業代行に留まらず、リアルタイムな経営管理やセキュリティ強化、属人化リスクの低減など、企業経営に直結する効果が期待できます。以下、こうした連携施策によって得られる代表的な7つのメリットについて解説します。
クラウド会計システム導入により日々の取引データが自動記録され、企業側でもリアルタイムに閲覧可能です。最新の経営状況を把握できることから、迅速かつ的確な意思決定ができるようになり、経営判断の精度が高まるでしょう。営業機会の損失防止にもつながります。
クラウド会計の導入で、ペーパーレス化が進み、紛失等による情報漏えいリスクが軽減されます。また、アクセス権限の設定やログ管理は、内部不正にも効果的です。加えて、アウトソーシングを活用した専門家のチェックで、業務の透明性も高まります。これらの相乗効果により、従来の手作業管理と比べても安全性が格段に向上します。
アウトソーシングとDX導入の過程で、経理業務のプロセスが整理され業務フローの標準化が進みます。これにより、事業拡大や人員増加に伴う業務の増大にもスムーズに対応できるでしょう。さらに、将来的に内製化へ移行する場合も、引き継ぎや育成がしやすい体制を構築できる点も強みです。
経理業務を特定の担当者に依存する「属人化」は、担当者不在による業務停滞リスクの高い状態です。アウトソーシングを活用することでプロの介在による業務標準化が進み、クラウドツールによる情報共有機能によって透明性も高まります。これにより、担当者交代時のリスクも最小限に抑え企業経営の安定化を図ることができます。
確実な給与計算と簡便な経費精算制度の整備により、従業員のストレスが軽減されます。ミスや遅延がない正確な支払いは、従業員の信頼感を高め、エンゲージメント向上にも寄与します。バックオフィスの整備は、企業の働きやすさに直結する重要なポイントです。
アウトソーシングによって、単純作業から解放された1人経理担当者は、データ分析やコスト管理といった付加価値業務に集中できるようになります。また、経営者が経理を兼務していた場合でもコア業務への専念が可能となり、限られたリソースを最大限に活用できる体制が整います。
税務や会計の専門家が業務を担うことで、税法や各種制度改正への対応が迅速かつ確実になります。常に最新の法令を踏まえた経理処理が行われるため、誤りによる罰則リスクを回避できるほか、帳簿の正確性も向上します。高度な専門知識を業務に取り入れることで、非常に大きなメリットを得られるでしょう。
経理業務の効率化に取り組みたいものの、自社に最適な方法を判断することは容易ではありません。そのようなときは、無料相談の活用がおすすめです。
現状の業務フローを専門家が分析し、適切なDX推進方法やアウトソーシング活用の診断を行います。また、導入にかかるコストや得られる効果を事前に試算できるため、無理のないスケジュールで計画的に進めることが可能です。
経理業務のDX推進は、単なる効率化にとどまらず、経営判断の質を向上させ、従業員の働き方改革にもつながる重要な施策です。クラウド会計ソフトの導入は、その第一歩に過ぎません。
次のステップとして、経理プロセス全体を支援するアウトソーシングサービスの活用を検討することで、初期投資を超える大きなリターンが期待できます。
神奈川 横浜・町田経理アウトソーシングオフィスは、経理・税務・経営に関するお客様のあらゆる課題を解決する総合会計事務所です。創業50年以上の歴史を持ち、約100名の専門家がお客様の事業を力強くサポートします。
約100名体制の経理・税務・経営のプロフェッショナルが、お客様の状況に合わせた最適なソリューションを提供します。複雑な課題も多角的な視点から解決に導き、お客様の成長を強力に後押しします。
会計・経理業務から給与計算、各種コンサルティングまで、DX化推進とアウトソーシングを支援します。これにより、お客様は本業に集中でき、業務の効率化と人件費などのコスト削減を同時に実現します。
最新のクラウド会計システムを積極的に活用し、経営数値のリアルタイムな把握を可能にします。これにより、迅速な経営判断をサポートし、事業の成長を加速させます。
経理・税務の基本サポートに加え、会社設立、相続、さらには医療機関や社会福祉法人に特化した専門的なコンサルティングも提供します。お客様の事業フェーズや業界に合わせたきめ細やかなサポートが可能です。
バックオフィスの改善や、経理・労務、経営に関するお悩みを信頼できる専門集団に任せたい経営者の方は、ぜひお問い合わせください。


経理体制の
ヒアリング(無料)

貴社の課題解決の
ためのご提案

ご契約
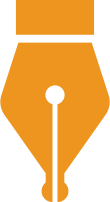
貴社の業務フローの
改善サポートの開始

経理代行業務の
開始