2026.01.30
副業時代に経営者が知っておくべき税務知識と「副業300万円問題」の最新動向
2017(平成29)年の「働き方改革実行計画」で副業・兼業の促進が明確に示されて以来、柔軟な働き方がしやすい環境整備の一環として、副業を認める会社は増加しています。そのため、経営者にとっても、副業…
決算業務とは、一定期間の経営成果をもとに決算書を作成する一連の作業です。決算業務には煩雑な作業が多く、手間がかかります。リソースに限りのある中小企業では、時間外労働の増加や他部門社員の支援を必要とするなど、業務過多が課題となっているところも多いでしょう。
本コラムでは、中小企業における決算業務の流れを確認し、よくあるミスを防ぐための具体策、効率化のための対策について解説します。
<目次>
決算業務とは?中小企業にとっての重要性
決算業務の流れ|3つの主要ステップ
決算業務でよくあるミスと負担が大きい処理3つの対策
決算業務を効率化するための4つのポイント
決算業務を効率化するアウトソーシングという選択肢
まとめ
中小企業では、1年に1度の事業年度末に年次決算を実施することが一般的です。年次決算業務は、日常的な経理業務とは異なり、決算特有の会計処理を行います。企業の財務状況を正確に把握し、適切な決算書を作成するためには、会計基準や税法の専門知識が欠かせません。
決算業務で作成する決算書は、税務申告や金融機関との取引にも活用する重要な書類です。また、適切な決算処理が企業の財務健全性を維持し、信用を確保することにつながります。万一、ミスや漏れがあれば、税務対応や資金調達、そして企業の社会的信用に悪影響を及ぼすでしょう。
決算業務は、勘定科目残高の確定、税金の計算、そして決算書の作成という3つのステップに分けられます。ここでは、3つの主要ステップの具体的な内容について説明します。
まず、日々の仕訳をもとに、決算日時点のすべての勘定科目の残高を確定することが重要です。年次決算では、月次での集計処理とは異なり、以下のような詳細な確認作業を行います。
次に、確定した勘定科目残高をもとに、消費税と法人税を算出します。税額を計算した後は、「未払消費税」と「未払法人税」として計上します。
最後に、以下の決算書を作成します。
これらの決算書は、経営分析や次年度の戦略立案、企業内部の意思決定などにも活用されます。さらに、企業の透明性を示す資料として、ステークホルダーとの信頼関係強化にも欠かせません。正確でわかりやすい決算書は、企業価値を高めることにもつながるでしょう。
決算業務には、専門的判断や細かな確認が必要な処理が多く、手間も時間もかかります。特に、「勘定科目残高の確定」は、財務データのベースとなる重要な作業です。ここでミスや漏れが生じると、以降の処理をすべてやり直すことにもなりかねません。
ここでは、特に注意すべき3つの主要処理とミスを防ぐポイントについて解説します。
棚卸資産とは、企業が販売や生産のために保有する在庫であり、期末日時点で未使用の商品・原材料・仕掛品を指します。ここに、備品等の未使用品は含みません。
棚卸資産は、決算日時点の数量と評価方法に基づく仕入単価を乗じて在庫額を確定します。現在試算表に計上されている棚卸資産金額を原価に振り替え、「確定した」棚卸資産金額を原価から棚卸資産へ振り戻します。
【仕訳例】期首商品在庫20万円が決算時に25万円と確定した場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 期首商品棚卸高(原価) | 200,000円 | 商品 | 200,000円 |
| 商品 | 250,000円 | 期末商品棚卸高(原価) | 250,000円 |
棚卸資産は、損益に直結する重要な要素です。記帳時点でミスがあると、決算に大きな影響を与えるため、その都度ダブルチェックを行い早めに修正しておくことが大切です。
減価償却費とは、固定資産の取得費用を耐用年数にわたって分割し、各会計期間に計上する経費のことです。固定資産とは、土地や建物、設備・機械など、企業が長期間使用し、かつ繰り返し収益を生むものを指します。
【仕訳例】器具備品400,000円、償却率0.5(定率法)の減価償却費200,000円を計上した場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 200,000円 | 器具備品 | 200,000円 |
固定資産の取得金額、償却方法、耐用年数、勘定科目などを正確に登録することが大切です。また、期中に概算計上を行う場合は、その数字を戻し入れたうえで確定額を計上しましょう。
経過勘定とは、支払いや入金のタイミングと、費用または収益として認識するタイミングが異なる場合に適用される会計処理です。
以下の基準に従い、適切な科目で計上します。
【仕訳例】決算月(3月)に消耗品25,000円を購入し、支払いは4月の場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 25,000円 | 未払金 | 25,000円 |
【仕訳例】決算月(3月)末日に4月分の家賃200,000円を支払った場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 前払費用 | 200,000円 | 現金預金 | 200,000円 |
経過勘定は、発生主義会計における「期間対応」の原則を守るために重要な処理です。ルールを明確化し、迷わず処理できるように仕訳時のチェックリストを活用すると良いでしょう。
決算業務は、日常業務と並行しながら、膨大なデータを正確に処理する必要があります。1人経理でもスムーズに進めるには、日々の業務改善と計画的な決算準備が不可欠です。限られた人手と時間の中で効率化する4つのポイントを紹介します。
決算業務の負担を軽減するためには、月次レビューの習慣化が効果的です。年次決算まで先送りにせず、月次決算を丁寧に行うことが年次決算をスムーズに進める鍵となります。
決算業務は、1年に1度しかなく、慣れていないと手順を思い出すのにも時間がかかったり、処理漏れや抜けが生じたりするリスクがあります。そういった状況を回避するために、業務マニュアルを作成しておくことが効果的です。マニュアルがあれば、他部門の社員もサポートしやすく、適切なダブルチェックが行えます。また、経理担当者の休職や退職があったときも、スムーズに引き継ぎできるでしょう。
決算業務は、経理部門だけでは完結しません。請求書がなければ残高が確認できず、営業部門の経費精算が遅れれば費用確定も困難になるため、他部門からの資料を提供してもらう必要があります。そのためには、決算業務に必要な資料を整理し、事前に他部門と共有することが重要です。さらに、経営陣が決算の重要性を周知することで、他部門も目的を理解し、協力を得やすくなるでしょう。
決算業務の作業を一覧化したチェックリストを活用すると、抜け漏れ防止に有効です。前年度決算からの変更点や注意点を記録しておくことで、決算精度を年々向上できます。
決算業務は決算期に業務が集中するうえ、簿記や会計の専門知識が必要不可欠です。1人経理では負担が大きく、処理ミスや日常業務の停滞が発生しやすくなります。
そこで、まずは日常業務にアウトソーシングを導入する方法がおすすめです。1人経理の課題である属人化の解消やチェック対象の強化ができ、専門性を確保しながら業務負担の軽減が図れるでしょう。さらに、残高の確定や税金計算など、より高度な専門知識が求められる決算業務は、税理士に依頼することで、最新の税制にも適切に対応できます。
日常的な仕訳記帳業務を委託することで、適切な仕訳作業と正確な記帳業務が実現します。本コラムで紹介したような「よくあるミス」リスクを回避することができるため、決算業務の効率化にもつながります。アウトソーシングは、業務プロセス全体の委託から作業単位の依頼まで、幅広く対応可能です。業務負担や専門性、予算も考慮し、適切なアウトソーシング範囲を慎重に検討しましょう。
また、税理士には、下記の業務を委託可能です。決算業務の効率化だけでなく、健全性の維持や企業成長にも貢献するでしょう。
プロの視点によるチェック体制が整い、正確性が向上します。また、クラウドツールと連携し、取引データ取得などを自動化することで、手作業によるミスや漏れがなくなります。
税務や会計の専門家のノウハウを活用し、適切な処理を実施できます。業務の質を高め、複雑な決算業務にも対応可能です。
煩雑な経理業務の負担を軽減し、繁忙期の残業を抑制できます。働き方改革に準じた労働環境を整えることにもつながります。
1人経理は、税法改正や制度改正があるたびに、自分で勉強しなければなりません。相談相手もなくチェック体制も整っていない中では、誤解やミスが生じるリスクも高まります。専門家のサポートを活用することで、適切な税務対応が可能となります。
特定の担当者に依存する属人化を防ぎ、再現性のある業務フローを構築できます。決算業務プロセスを標準化することで、担当者変更時のスムーズな引き継ぎや業務の一貫性を確保にも役立ちます。
1人経理の繁忙期における業務過多、それに伴う日常業務の停滞が起こりにくくなります。また、他部門の社員が応援に回る必要もなくなり、経営や営業などコア業務への注力が可能になるでしょう。経理業務の効率化が、企業全体の効率アップにも寄与します。
アウトソーシングには、多くのメリットがありますが、その分コストが発生します。アウトソーシングする業務を精査し、費用対効果を慎重に検討することが大切です。
さらに、自社の規模や業種、業務内容に合った業者を選定することも重要です。類似企業の支援実績が豊富な業者なら、蓄積されたノウハウを活用し、最適な方法を提案できます。そのため、契約を検討する前には、無料相談を活用し、自社に最適な依頼範囲を見極めましょう。
無料相談の活用については、以下のコラムでも詳しく解説しています。
【経理アウトソーシングの比較検討】無料相談を無駄なく活用するポイント
決算業務は、経理の中でも特に重要で負担の大きい業務です。正確性を高めることが重要で、ミスがあると財務情報の誤りや納税額の過不足が生じます。不正確な財務データでは、経営判断を誤ることにもなりかねません。
また、決算資料は金融機関との取引に関わり、資金繰りにも直結します。そのため、可能な作業は前倒しし、業務フローを事前確認することで、より効率的な決算業務を行えます。
自社内で手に負えない場合は、日常業務にアウトソーシングを導入する方法が効果的です。
また、決算業務を税理士に委託するという選択肢もあります。
弊社では、貴社の環境に適したご提案・サポートをさせていただきます。
さらに、当サイトを運営するYMGコンサルティングラボのグループ会社である林会計に所属する税理士との連携を図ることも可能です。
もちろんご相談内容は守秘義務により厳重に守られますので、ご安心ください。
完全無料!オンライン面談OK!まずはお気軽にご連絡ください!



経理体制の
ヒアリング(無料)

貴社の課題解決の
ためのご提案

ご契約
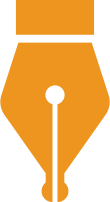
貴社の業務フローの
改善サポートの開始

経理代行業務の
開始