2026.01.30
副業時代に経営者が知っておくべき税務知識と「副業300万円問題」の最新動向
2017(平成29)年の「働き方改革実行計画」で副業・兼業の促進が明確に示されて以来、柔軟な働き方がしやすい環境整備の一環として、副業を認める会社は増加しています。そのため、経営者にとっても、副業…
働き方改革は、制度を「導入すること」が目的ではありません。現場に根づき、社員の意識や行動が変わるよう「運用」することが重要です。本コラムでは、中小企業がよく陥る5つの失敗例を具体的に紹介しながら、実効性のある対策を提示します。
「働き方改革」というと、法令遵守や制度導入に注目しがちですが、本質は改革後の「運用」にあります。つまり、何を導入するかではなく、何のために運用するかを考えることが重要です。
企業ごとに課題は異なるため、他社の成功事例をそのまま取り入れることが、自社の成功につながるとも限りません。期待する効果が得られないばかりか、混乱を招き、社員満足度が低下する可能性があります。表面的な改革から一歩踏み込み、自社の課題を理解したうえで、企業文化や業務プロセスの根本的な見直しをおこなうことが重要です。
働き方改革は、企業の生産性向上と多様な人材が働きやすい職場環境づくりを目的とした取り組みです。関連法案の施行は2019年4月から始まっており、以下の3つを主軸としています。
時間外労働の上限規制:時間外労働は、原則として月45時間・年360時間、特別な事情がある場合でも年720時間以内を上限とする
年次有給休暇の取得義務化:年10日以上の有給休暇を持つ労働者は、最低5日の取得が義務づけられる
同一労働同一賃金の推進:同一の労働をおこなう場合、正社員と非正規社員の待遇格差を是正する
働き方改革に取り組む際のポイントは、企業成長と社員のワークライフバランス向上を両立させることです。そこを考慮せずに改革を進めても、期待した通りの効果は得られないでしょう。それどころか、業務の複雑化や従業員の負担増につながるおそれがあります。
よくある失敗例から自社に共通する課題を見極め、適切な対策を検討しましょう。
トップダウンの一方的な押しつけ、あるいは現場への丸投げは、代表的な失敗例といえます。特に、経営陣が働き方改革の重要性を理解していない場合、改革は表面的なものになりがちです。また、現場の社員にとっても「何のために導入しているのか」がわからず、反発が生まれやすくなるでしょう。
まず、改革の目的や目標を明確にすることが重要です。「なぜ、働き方改革が必要なのか」「何をどうすることで、どのような会社を目指すのか」を明文化し、社内全体で共有しましょう。できるだけ具体的にわかりやすく説明することで、企業ビジョンの共有が可能となります。
事前アンケートやヒアリング、ブレインストーミングなどをおこない、現場の声を聞くことも重要です。トップの思いと現場の実態をすり合わせることで、有意義な改革案を作成できます。また、継続性を高めるためには、現場の声を定期的に集める仕組みの構築も必要です。
将来のビジョンと現場ニーズに合った「新しい働き方」を策定できたら、経営者が率先して実践しましょう。トップ自ら改革を実施する姿を見せることで、社員それぞれの改革意識が高まり、モチベーションにつながります。
同じ社内といえども、部門ごとに業務内容や労働スタイルは異なります。社内全体に同じ改革を一律に適用させようとすれば、無理が生じて当然です。例えば、バックオフィス業務はテレワークを含む柔軟な働き方が可能ですが、製造や開発部門は現場作業が不可欠、営業は顧客との調整が必要になるでしょう。
多様な働き方について、下記コラムでも詳しく解説しています。
https://keiri-outsourcing.com/column/column-8712/
「多様な働き方」にはどの方法で対応すべきか
例えば、フレックスタイムやテレワークなど複数の選択肢を提示できる環境を整え、企業全体で統一する部分と各部門に委ねる部分を設けます。業務内容や職種、時期などに応じて最適な組み合わせを選べるメニュー型設計が効果的です。
いきなり全面的に改革するのではなく、まずは小規模なテスト運用をおこないましょう。段階的に導入することで、問題が生じても早期に解決可能です。また、現場のフィードバックを得ながら調整することで、最適化を図りながら導入できます。
働き方改革を支援するやツールを導入しても、十分に活用されず自然消滅するケースがあります。その原因として、ツールの使いにくさや業務とのミスマッチ、研修不足による操作の不理解などが挙げられます。また、既存の業務フロー変更に対する抵抗感も、見逃せない要因の1つです。
ツールを選定する際の前提として、事前にまとめた自社のビジョンや課題に対応するものを選ぶことがあります。そのうえで、自社の業種や規模と合っていること、必要な機能があること、直感的な操作ができることなども重要な視点です。ツール選定には専門的な知識と経験が必要なため、プロに相談すると安心です。
取り組みを始める前に、全社員を対象とした説明会や研修・トレーニングを実施し、周知と理解を広めます。また、導入後の問題に迅速な対応ができるサポート体制の構築も重要です。専門的な分野は外部のプロに任せる場合は、社内窓口を設け各部門にリーダーを置くと、問題の把握やサポートとの連携がスムーズにおこなえます。
時間外労働の上限規制は稼動時間の縮小につながるため、頭を悩ませる事業所は多いでしょう。表面的に残業時間だけを減らしても、業務量や業務プロセスがそのままでは「持ち帰り残業」や「サービス残業」が横行するおそれがあります。そうなれば、業務の質低下や社員のストレス増を招くことになりかねません。
時間外労働を根本的に減らすためには、業務プロセスの最適化が不可欠です。そのためには、企業全体の業務フローを見直し、重複やボトルネックを解消し、効率化を図ります。業務プロセスの最適化には専門的なスキルを必要とするため、外部の専門家に依頼することが有効です。
労働時間の見直しには、業務量を可視化とチーム全体での共有がポイントとなります。作業負担を平準化し、ガントチャートやカンバン方式、タスクリストなどを組み合わせ、自社に合った管理方法を導入すると効果的です。
働き方改革における改善活動の進捗情報は、経営陣のみ、部課長以上など一部の管理職だけではなく、社内全体で共有することが大切です。いつでも誰もがリアルタイムの進捗情報を把握できることで、モチベーション向上や継続性に貢献します。
働き方改革におけるビジョン、改善プロセス、進捗、導入ツールの効果や活用例などをまとめて共有できる場を設けましょう。目的を再確認したいとき、ツールの操作を知りたいとき、現時点の進捗を把握したいときなど、さまざまな目的で利用できます。知りたいときにすぐわかることが、モチベーションの維持に効果的です。
導入後も継続して現場の声を拾い、社員の反応を把握しておくためには、定期的なフォローアップがかかせません。1on1ミーティングや目安箱など、幅広い方法を揃えておくと、言いにくいことでも伝えやすくなります。
働き方改革を成功させるためには、適切なツール選定から導入サポートまで、専門家の知見を活用することが効果的です。それぞれに特化した専門家もいますが、説明の手間やコストを考えると、一貫して頼めるところが良いでしょう。
働き方改革に効果的なツールを選定する際は、一度でも客観的なプロの意見を聞いておくことをおすすめします。さまざまな企業へのツール導入サポートをおこなった実績のある業者ならば、自社の規模や課題に適したツール選定に有効なアドバイスができるでしょう。
ビジネスチャットツールやWEB会議システムなどのコミュニケーションツールは、社内外のコミュニケーションを円滑にし、情報共有をスムーズにします。これにより、テレワーク環境が整い、時間や場所にとらわれない働き方を実現できます。
勤怠打刻から労働時間管理、給与計算までを一貫しておこなうシステムを活用することで、テレワークやフレックスタイムの導入がスムーズになります。また、同時に給与計算に関わる1人経理担当者の業務効率化を実現し、時間外労働削減にも貢献するでしょう。
経費精算業務の効率化により、1人経理担当者および精算を必要とする社員の手間が大幅に軽減します。スマートフォンアプリからの領収書撮影機能で、外出先から申請作業が完結します。領収書の添付漏れや転記ミスがなくなるため、経理側の処理もスムーズになり、双方のストレス減も期待できます。
導入サポートを依頼すると、専門知識を持つスタッフが制度やツールの選定から導入、データの移行作業、初期設定などをおこないます。また、導入後のヘルプ・サポートや、社員への研修・トレーニングを委託するプランもあります。部分的な依頼ができることも多いため、予算や目的を伝え、相談すると良いでしょう。
働き方改革を進めてもなおリソースが足りず、手が回らない業務がある場合は、アウトソースするのも効果的です。経理業務のアウトソーシング業者では、業務プロセスまるごとから部分的な作業まで、柔軟に対応していることが多いため、自社に状況に合わせて利用することが可能です。
働き方改革は、制度やツールを「導入すれば終わり」ではありません。導入後の運用フェーズこそが、改革成功のための勝負どころとなります。
中小企業のようにリソースに限りがある環境では、誤った設計や運用によって、大きな混乱や反発を招くことがあります。だからこそ、本記事で紹介したような失敗を未然に防ぎ、自社に合った対策を講じることが重要です。
働き方改革の成功は、制度導入ではなく運用の質で決まります。中小企業が陥りやすい5つの落とし穴を理解し、適切な対策を講じることで、より効果的な改革を実現できるでしょう。
働き方改革では、自社の課題を理解し、適切なツール選定から導入サポート、業務プロセスの最適化までの包括的な支援を受けることがポイントです。
これにより、限られたリソースでも最大の効果を得ることができます。
神奈川 横浜・町田経理アウトソーシングオフィスは、経理・税務・経営に関するお客様のあらゆる課題を解決する総合会計事務所です。創業50年以上の歴史を持ち、約100名の専門家がお客様の事業を力強くサポートします。
約100名体制の経理・税務・経営のプロフェッショナルが、お客様の状況に合わせた最適なソリューションを提供します。複雑な課題も多角的な視点から解決に導き、お客様の成長を強力に後押しします。
会計・経理業務から給与計算、各種コンサルティングまで、DX化推進とアウトソーシングを支援します。これにより、お客様は本業に集中でき、業務の効率化と人件費などのコスト削減を同時に実現します。
最新のクラウド会計システムを積極的に活用し、経営数値のリアルタイムな把握を可能にします。これにより、迅速な経営判断をサポートし、事業の成長を加速させます。
経理・税務の基本サポートに加え、会社設立、相続、さらには医療機関や社会福祉法人に特化した専門的なコンサルティングも提供します。お客様の事業フェーズや業界に合わせたきめ細やかなサポートが可能です。
バックオフィスの改善や、経理・労務、経営に関するお悩みを信頼できる専門集団に任せたい経営者の方は、ぜひお問い合わせください。



経理体制の
ヒアリング(無料)

貴社の課題解決の
ためのご提案

ご契約
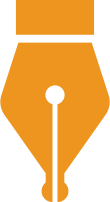
貴社の業務フローの
改善サポートの開始

経理代行業務の
開始